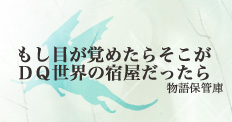
●一つの邪悪 心は、いつだって一つではなく、肉体はまるで入れ替え可能な入れ物だ。 やると思えばどうにでも、ある水準にまでは性格すらも切り替えられる。 誰にだって気軽にだって出来るわけではなく、俺にとって初めての試みで、自分の意思として今、違う自分を作り出している。 うまくいっているように思えるが、実際、これがどうとにもならず逆に苦しみを増やしているんじゃないかとさえ、考える。 けれどこの通り過ぎる時間を遣り過ごすには、そうやってあの出来事たちを抑える必要があった。 でなければ、まるでそこに意思とは関係が無い一人を作ってしまうからだ。 「お前達の主人はどこにいる」 「お、教えるものか。なんで人間になどあの神聖な……」 「そうか」 奇跡の剣がボウと空間へ亀裂を立て、死絶寸前の醜い魔物の頭上へと鋭く研ぎ澄まされた刃を触れる。 骨を砕き肉をえぐる悲鳴は、もう数千と聞き慣れた。べたりと這う色の無い塊は、ざらざらと巡るしぶきを落としている。 俺はいま、魔王へと一直線に向かうべきとし、そうしようと進んでいた。 襲う魔物も見つける魔物も全てを薙ぎ倒しながら、まっすぐとライフコッドであっただろう残骸を踏み、山を谷を越えてきた。 なのに、あるはずの邪悪でいっさいが神聖ではない往くべき根城が、見つからない。 もう数日は同じところをぐるぐるざつざつと、岩や土や水も草も樹も枝も踏み続けている。 「またきたか……」 独特の感触をもたらす嫌な気配を感じた。 薄っぺらな声をあげ、少し離れた場所でいくつかの影を呼び出す蠢くもの。 この地ではよくある風景で、辿り着いた黒い── もはや俺には黒い塊にしか見えない魔物達は凝りもせず襲ってくるのだ。 「最近ここらで暴れている人間とはお前のことか。 どうも、信じられん。なんと小さな存在であることか。 それにしてもお前、よくここまで生きてこられたな」 似たような言葉を今日だけで何十回と聞いただろう。 こいつらは、同じ言葉を下等な魔物全員の意識間で共有しているのじゃないか。 だから同じ文句しか言えず、同じ行動しかしないのではないのか。 そうなら、こいつら魔物達は単に姿かたちが違っているだけで、ぜんぶ運命共同体ということに成る。 結局は魔王の存在たった一つが、それらにたった一つのどうやりようもない邪悪を与え、動かしているに過ぎないのだ。 「おい。なんとかいえ。せっかく、お前に喋る機会を与えてやっているのに。 俺達を楽しませろ。もう人間という餌がなかなか見つからないから、我々は退屈しているのだ」 「そうか。逆に言わせてもらうが、ならばお前達こそ、この俺を楽しませてほしい。 これは俺の頼みだ。どうしてもというわけではないが、それなりに楽しませてはくれないだろうか」 「こいつ……! 黙っていれば生意気を言う。 お前の願いを叶える事などまっぴらだが、ゆっくり痛めつけてその口を後悔させてやろう。 どうだ。少なくとも俺達の望みは叶うのだ。 ああ、そうだ。もしお前が、痛みを好むのならお前の願いも叶うというわけだ。ガッハハハ!」 大きな黒が笑うと、周りの中くらいの黒たちもぎゃあぎゃあと笑った。 いったい、どんな魔物なのだろう。 俺の目に映るごわごわと動くソレは、まるでぼんやりと反射する黒い生命体にしかわからない。 こんなものを生命体と呼ぶにも、まったくがふさわしくなどなく、先刻できたばかりの残骸のほうがいくらか高尚だ。 「痛みなら、もう十分にある。好きではないが、今では嫌いでもない。 生きている限りどうしたって痛みは発生するのだから、嫌っていても逃れられない。 俺はそういった感触とどう付き合っていくのかが、大事なんだと思う。 けれどまだ、俺に答えは見えていないから、こうやって自分を隠して歩く。 なぁ、いい話題だ。 なのに、お前たちには理解できないんだろう。 なぜなら、お前等は思考もまっとうな感情すら持たず、あわよくば生きているだけの、下等で下劣でただ動く肉なのだから」 ぐっと、邪悪な波動がこの淀んだ空気を波立てる。 言った台詞はどうも、黒い者達を刺激したらしい。 もっともだと思えるから、少し可笑しかった。 「お前が、殺されるのは、既に決定していることだから、こうして会話でもしてお前を死の緊張から解いてやろうと、してやっているというのに。 良かったな、俺は他のやつらと違って、気が大きいんだ。 だが、もう俺はお前の叫びや掠れた声や血や肉を喰いたい。 イライラとする身体を慰めてやりたいと思う。おい、人間よ」 「ああ。そう出来るのならすればいい。その前に、俺の話を聞いてもらえないか。 逃げ惑い地を這いずりながら命乞いをし掠れた声で空に助けを求め、最後はこの両手でお前にすがると約束する」 黒い魔物はふふんと鼻を鳴らした。 今の言葉が相当に楽しみで、今にもすすりたそうに感じる。 次の声は喜びで微かに震えていたのだから。 「おお。いいだろういいだろう。なんでも言ってみろ」 「ありがとう。では聞くが、魔王の元へはどうやって行ったらいいんだ。 さっきまで見えていた城が、まるで見当たらなくなった」 「魔王様の…… お前、約束は必ず守るんだろうな」 「いまさら、嘘を言ったってどのみちお前達に殺されるんだろう」 「それもそうだな。よし、教えてやる。 魔王様の城は、美しく強大な邪悪の魔力によって守られているのだ。 だから、ルビスなどという神にすがる人間に見えるはずなどない、というわけだ」 「なるほど、そういう事か。 じゃあ、俺を案内してはくれないか」 「バカな。誰がそんな事をするというのだ。 それより俺はもう我慢が出来ん。十分話してやったのだから、お前を約束のためじわりじわり殺そう」 大きな黒は、何か武器を持っているようだった。 それを大きな身振りで構え、左右にまた大きくゆっくりと振る。 どうやら中くらいの黒たちに手を出すなと、合図しているらしかった。 「さぁ。命乞いをしてみろ」 黒い武器は、剣のようでそれがそこそこの速さで俺を突こうとしてくる。 俺もまた剣を抜き、その暗闇からにゅうと出る刃を激しく叩き、弾いた。 黒の魔物は驚いた様子を見せ、やや狼狽しながらも強気を見せる。 「お前! 約束したではないか! 抵抗など、そんな意味の無いことなど……!」 「約束はした。だが、お前らが守らないものを俺が守る道理などない。 ついでに言うが、殺されると決まっていたのはお前達で、俺ではない」 こいつら魔物は、自分の都合の良い事に関してだけは気安く「約束」などという言葉を使う。 今までに守ったことの無い単なる飾りと化したその言葉を、今度は人間の俺にやられたのだ。 怒りは分かるが、その意味など理解できようもなく、やはりこいつらは哀しい塊にすぎない。 「や、やくそくが──」 まっすぐ衝き立て、大きな黒の首をゴツリと刎ね、更に四方八方へ刃を振るい全てを小さな個々とする。 中くらいの黒たちが一斉に飛び立ちばらばらに、やがて重たい雲の中へと消えていく。 「さて。どうしたらいいものか」 その場で少しの間を考えそのうち俺は元来た路を引き返し、山を谷を越え始める。 城を暴く方法が無いのもあるが、魔物を易々と粉砕していくことに少しばかり疲れていた。 肉体的な痛みや傷は奇跡の剣の効能のおかげで回復できるが、疲労といったものは自身で癒さなければならない。 ここより近いライフコッドの跡地で身体を休め、気力を充実させようと思った。 ●精霊の言葉 あれからどのくらいが経ったのか、村を見てそれを実感することは出来ない。 でこぼこな焼け色のブロックで作られた、こじんまりの家にそれらをおうおうと取り囲む緑に濡れる木々。 高台から見下ろす外界は霞もせず透明に感ぜられ、肺に吸い込む新鮮な空気が口や喉と身体をも浄化してくれた。 なのに、目に焼きついているはずのそんな情緒溢れた景色はいまや、石とほこりと土煙に姿を変えてしまったのだ。 今のライフコッドは、廃れた家屋と潰れた通りがただ静かな音で在る、まるで経年の変化とは無縁の形相だ。 メルキドでの出来事。 ゴールデンゴーレムが立ち去った後、いくつかの亡骸を丁寧に埋葬した。 残念だけれど、ルビスとフーラル以外はよくわからない塊だったから、一つにまとめて。 最後にルビスを抱き上げたとき、ふと、奇妙な感情を憶えどうしようもなく悲しかった。 ここにまた、斃れてしまった人がいる。 そっと深く冷たく暗く、掘り下げたその場所へ身体を降ろし、自らの血液で固まるその髪を二つ三つ撫で話しかけた。 「俺に何か出来たろうか」 ……ルビスの謡う声は、もう聞こえず。 残されたこの身は何をしてこうなったのか。 結局、教えてはもらえなかった。 何日かを荒れたライフコッドで過ごし、この間はまったく魔物と血を洗う戦いなどもなく、比較的平穏だった。 些細なことで、小さくため息のような言葉を吐けばそれがそのうち大きな思考となる以外は。 自分でして来たたくさんの事が果たして何の意味だったのだろうと、結局はその時点で行き詰まりとなる。 気力を持ち直そうと考えていたがそう出来ず、前へ進む気にもならなかった。 「もしかすると、こうなることが初めから決まっていたのかもしれない」 「ならば神であるルビスにもわかっていたはずだ」 「ではなぜルビスまで死に、今たった一人なのか。わかっていれば全部回避できたはずなのに」 「つまりは、誰もこうなることなどわかってなんかいなかった」 「俺は、今何の為にこうしているのか」 まるで解らなかった。 とうに理解を超えていたのだから畢竟、なにを導き出すこともない。 ある夜。 いつものように奇跡の剣を振るい石ころを蹴飛ばし地面を蹴り付け、身体を痛めつける。 常に身体を動かしこなれていなければ、持つ力に飲み込まれてしまいそうだからだ。 力に翻弄されてしまえば意思を保つことなど出来ず、気が付けばいつかは魔物に殺されるだろう。 ルビスに言われた"強くなれ"の言葉だけ、頑なに信じて疑わない。 そもそも、強ければ今の孤独など無かったはずなのだから。 強ければ今を打開出来るのではないかと、そう解釈もしている。 現状に失望しているはずなのに死にたくないと思う自分も可笑しい。 強くないのだから居なくても変わらないという思いも在る。 それだけならばただそこらの道へ身体を放り出し、強そうな魔物に出会うまで何もしなければいい。 そうすればいつかはこんな日々も終わるはずだけれど、そうする勇気も無かった。 いつでも心は、この二つの矛盾で苦しくなるから、何も考えない時間が必要だった。 つまり、日々の厳しい自己鍛錬で身体を動かしその間だけは忘れようとしている。 そんな風に変わらない気持ちで鍛錬しているつもりだった。 けれどこの日に限ってからっぽの気持ちを抱き、力はすんなりと思う通りとなり、抑える独特の震えに怯えることも無かった。 昨日までは鍛錬をしていても、どうしたって様々なことを考えていたというのに。 どうしても身体はこれまで以上にすいすいと動き、曇りなどなくなったように明るい。 だが、これで魔王に太刀打ちできるかと言えば、はっきり無理だろうと言える。 この幾日か、これ以上は強くなれないのではないかと考えていたが、ついにここが自分の限界なのかと悟ったその時── 「……やっと極めたな。我々はずっとお前を見つけ、起こるその瞬間を待っていた」 意識へと語りかけてきたソレが、どこからという間も無く身体へと流れ込んでくる。 どこにも気配や姿など見えず、卑怯なくらい一方的なソレが容赦なくチクチクと背中のほうへ刺し込む。 激しくもがき抵抗するも、ついにはとうとう、入られてしまった。 「なにものなんだ?!」 「案ずるな。我々はルビス様に仕える最後の精霊。 お前の中にある"希望"を開放させるため、ここまで様々な地を探しお前を見つけた」 「何を探してどうして俺なんか」 「オリハルコン── どうしても必要な物だというのにお前は手放し深い暗闇へと堕ちた。 まったくそれは鍵となるのだからどうしても手に入れなければ成らなかった。 そのために仲間の精霊が二人も犠牲となったのだ」 「そのオリハルコンがどうだっていうんだ。手にして戦っていたって魔王には一切が通じやしなかった」 「オリハルコンはお前の中にある"希望"…… ルビス様の言う"真の力"を起こすために必要なのだ」 突如現われた声に、入り込んできた精霊達の言う言葉に、まったく嫌気が差す。 オリハルコンは真の力を発揮するのに必要なんだと、ルビスからはすでに聞いている。 だが真の力を発揮した結果は散々たるもので、結局メイを死なせルビスまでも土へ返してしまったではないか。 今更そんな事を言われてもまったく、聴く耳も持たない。 「お前達の言うことはルビスから何度も聞いているし、結果こうなっているじゃないか」 「あの時点で魔王がお前の元へ現われるなど、我々の予想出来なかった事なのだからそれはどうしようもない。 お前はなにも、間違ったことなどしていないのだ。 自分の限界を知った今、ようやくオリハルコンによって真の力を発揮できる本当の準備が出来たと言える」 「信じられないな。ここまで生き残りオリハルコンをどこからか見つけてくるくらいに強いお前達が、世界を救ったらどうなんだ」 「……それは出来ない。我々はすでにオリハルコンとの融合を終えルビス様の息のかかった者としか接触できない。 実体はすでに無いのだ。剣を扱うことも魔法を使うことも出来ない。 もし実体を保っていたとしても、真の力を秘めるお前にしかやはり、世界は救えないだろう」 「……お前達が今の俺に入れば真の力が発揮できると、そうなのか」 「そうだ。ただし、オリハルコンは使えない。状況が変わってしまったのだから併せて状態も変えなければならない。 お前は、魔王の元へと赴き魔王の力を弱める必要がある。それが真の力を開放する条件でありお前のするべき仕事だ」 「じゃあ…… ルビスが強くなれといっていたのは、魔王の力を弱めるためだと。 そうすれば隠された真の力が発揮できるのだと、そういう事なのか」 「その通りだ。お前がこれまで真の力だと考えていたのは、お前の感情と魔力に反応するオリハルコンの特性から無理に引き出された中途半端な力だ。 ルビス様がどう説明されたのかはわからないが、オリハルコンは真の力が解放される瞬間に必要なものであり、お前の戦いに必須ではない。 さあ、わかったら我らを連れて進むのだ。お前の今の力で十分、真の力を解放する可能性は残されている」 これが限界で明らかに魔王になど立ち向かえないというのに、それでも真の力が発揮されるという。 これ以上どうしようもないというのに、俺は最早その時になると別の生命体にでもなるというのだろうか。 それでも、俺にはなにも見えていないから、精霊達に従って動くしか先が無い。 だが、進み始める前に確かめておきたいことがあった。 「……わかった。いう通り魔王の元へいく努力をしよう。 だが解るなら教えて欲しい。どうして俺がここにいるのかを」 ●存在 「ルビス様から何も聞いていないのか」 「聞く前に、ルビスは死んだんだ」 「ふむ…… では教えよう。だが聞いたからといってお前の今後は一つしかないということを忘れないでもらいたい」 「それはわかっている。ただ俺は、何も知らず終わるのが嫌なだけだから」 「わかった。まずお前は、この世界の人間ではない。これは解っていると思うが、お前が聞きたいのはなぜお前だったかという事なのだろう。 結論から言うと、お前は偶然選ばれたに過ぎない」 今更、この世界に居るという事にショックなど受けはしないが、偶然だと言われるのはいい気がしない。 それを精霊に咎めると"お前であったのは今にして思えば必然だったのだろう"と、一応補足してくれた。 「魔王がいのちの源を自身の力に変えているというのは、知っているか」 「あ、ああ。以前にルビスから聞いた」 「いのちの源は輪になっている。始まりと終わりはそうして繋がり常に循環している。 魔王は、例えるならば終わりだけを切り離し自らの力へ取り込むことに成功した。 邪神の像という禍々しい像によってだが二つ目の世界の物であり、魔王がどうやって手に入れたのかは解っていない。 そこからいのちの源の均等が乱れ、神々が九つ目の世界を創るときお前の世界のいのちの源と一瞬だけ繋がってしまった。 その影響で受け引きずり込まれたのが、お前だ。 これはいのちの源が、別の次元のいのちの源へ出した助けだとも考えられる」 「神々が俺を引きずり込んだわけではないのか……」 「その時点ではまだ神々に魔王の存在も輪の乱れもわかってはいなかったのだ。 話を戻すが、世界はいのちの源を元に創られるから、魔王に邪魔された状態では不安定な九つ目の世界しか創る事が出来なかった。 それがこの、今居る世界だ。ここは神々の意図する新たな世界ではなく、過去全ての世界が混在した世界になっている。 本来なら不完全な世界は破壊し、新たに創り直すのだがそれすらも出来ない。 この事について神々は疑問を抱き調査し、ようやく魔王と乱れを知った時にはすでに手遅れだったのだ」 話を中断させ深呼吸し、混乱した頭の中を整理した。 理解しがたいが、ルビスの遣いである精霊達の言葉だから間違いないのだろう。 今居るここは失敗作で、俺はルビスに連れてこられたと思っていたが実際は違ったのだ。 ルビスではなく神々であり、いのちの源とやらが引きずり込んだ。 「……手遅れだと知り悲観する神々の目に、漂うお前の姿が映った。 お前は、お前の世界とこの世界との間をおよそ数百年を魂となり漂っていた。 お前たちの世界ではほんの一瞬なのだが、こちらの世界とは時間の流れが違うから気に病むことは無い。 漂うお前に神々は驚き、その原因を先ほど話したように推測した。 そして、お前がこの世界の人間とは構造が違うことも発見した。 基本は同じだが、秘める潜在能力と記憶に違いがある。そのおかげで、お前はこの世界における制約を全く受けることが無い。 そこに神々は目をつけ、お前の世界では使われない精神空間へ希望を閉じ込めることに成功した。 その希望こそが真の力。だからルビス様はお前を守り、お前に真の力を解放できるように強くなれといった」 「……その、閉じ込められた真の力とはいったいなんだ」 「それは我々精霊にはわからない。ただ、魔王の力を弱める── 邪神の像を破壊するくらいにお前は強くならなければいけない。 そうしなければ魔王はいつまでも永遠に力を弱めることが無いからだ。 それが神々がお前に与えた肉体の限界でもある。その限界を乗り越えるため、真の力が必要なのだ」 「……神が、魔王を倒すといったことはしないのか」 「それは出来ない。これも制約なのだが、世界の危機は世界の住人によって救われなければならず、その為の手助けであれば可能だ」 なんとも勝手な話だが、俺はここまで結局のところ神々の思うように動かされている。 当初の目論見とは違ったのだろうが、それでも決められた終着点へと近付いている。 ここまでで、俺がどうしてこの世界の住人になってしまったのかが解った。 解ったところでやっぱり、どうにもならないしこれ以上難しい話を聞いてもたぶん理解など出来ないだろう。 精霊達もここまでしか解らないというのだから、この話は終わらせることにして気にかかっていることを聞くことにした。 「魔王を倒したら、それでどうなるんだ」 「この世界は破壊が始まり、この世界と繋がる別の世界も全てが何もない状態になる。 いのちの源によって何百何千何万年かかるかはわからないが、徐々に修復され記憶に従い九つ目を創る前まで戻るだろう。 神も全ての生物も、全てが元の通りになるわけだ。ただし、魔王の存在はあるべき形へと修正される」 「俺は」 「お前については…… どうなるかわからないのだ。 神々の見解ではおそらく、元の世界へ戻るであろうと聞いているが果たして──」 何の感情も起こらなかった。 意味は何度も、これまで幾度と無く口の中で繰り返した言葉。 「帰れないかもしれない──」 そんな言葉自体が存在しているのかどうかすら、危うく受け止める。 繰り返し反芻し、やがて実感としてこみ上げるまでの間、まったく表情一つ変わっていなかったに違いない。 現実味を帯びないとはまったく、こういう事なんだろう。 これが答えなんだと気付くと今度は笑いがこみ上げてくる。 ずいぶんと久しぶりの、大笑いだった。 笑うしかないとは、よくいったものだ。 「お前が何を笑っているのかはわからないが──」 精霊達の言葉を遮るように、はぁと笑いを止め声高に言った。 「わかってる。わかってるよ。 やらなきゃならない事はよく、わかってる。 少し落ち着いたら出発しよう」 無理に落ち着かせているように見えたに違いない。 だが実際、大笑いのおかげで随分と落ち着きを取り戻していた。 ここまで持ってきた不安は、笑いと共に瓦礫にした気になれた。 「これでいいのだろう。こうする事が俺にとってもみんなにとっても、残された手段なのだろう。 やるだけやって、それから考えればいいんだろう」 精霊達の出現と会話ですっかり落ち込んでいた心を取り持ち、ようやく道が見えてきたように感じる。 昨日までとは違いすでに道は開かれ、あとは進むだけなのだ。 「我々はこれよりお前の深い場所へオリハルコンと共に沈み込み、魔王の弱った瞬間をもって真の力を解放することとなる」 「なんだ。お前達はずっと話し相手になってくれるわけじゃないのか」 「真の力の解放は、神々が考える瞬間では無くなってしまった。それに加え魔王の力も日々増大し弱った瞬間とはいえ影響を受けるだろう。 時を確実にするため我々の残る力を振り絞り開放させなければならない」 「という事はまた俺一人で魔王の城を探さなきゃならんというのか……」 「いいや。お前が居座っていた場所に城は隠されている。そこでマジャスティスを発動させれば良い」 「マジャスティス……! だが、俺に魔法は扱えない……」 「考える必要は無い。対策はルビス様がすでに講じてくださっている。 とにかくまず、その場所へと向かうのだ」 「行けばいいわけだな、その場所へ。じゃあ早速行くが、お前達はいついなくなるんだ」 「今すぐだ。こうして会話をすること自体が消耗するものだからな。 いいか。まずは城を暴くのだ。その後なんとしても魔王の元まで行き、邪神の像を破壊しろ」 「しかし俺はその邪心の像とやらを知らないが」 「行けばすぐわかるだろう。お前の目に映る禍々しい像がそれそのものなのだから」 「わかった。とにかく像を破壊すればその先はどうにかなるってことだな」 「では、我々はこれより深に潜む。未来はお前に任せたぞ……──」 精霊達の言葉は聞こえなくなり自分の心の鼓動だけになる。 ここから、あの幾度も戦い続けた魔物の巣食う谷底へ向かうのだ。 魔物などは何も恐ろしくなど無い。 今となっては何が来ようとも負ける気などはしない。 「行って、さっさと終わらせるかな。とにかくやらなきゃ何も終わりやしない」 荷物は奇跡の剣と旅人の服だけ。 身軽さと戦いやすさを追求していくと自然にこうなる。 剣をヒュンと振り、全てを終わらせるためライフコッドの奥を抜け谷底へと向かった。 ●マジャスティス 一日かけて辿り着いた先には、なんの違和感も無く巨大な崖がそびえている。 それを下から眺めているわけだが、根拠があってこの場所を選んだわけではなかった。 他と比べ魔物が多量に現われるから、鬱憤晴らしの為だけにあの時は居座っていただけだ。 再び来てもやはり変わりは無く、魔物の激しい攻撃に晒されるだけだった。 「ここが本当に城の入り口なのか……!」 ぎゃあぎゃあと襲い来る魔物を斬り払いながら、講じられたというマジャスティスを待つ。 そうやって数十分を跳びまわり、すっかり場所を間違ってしまったかと思う頃、周りの雰囲気が怪しくなる。 「この気配。邪悪ではないがなんともいえない……」 最後の一匹へ剣を突き刺し止めを刺した瞬間、すぐ隣の空間が歪みぼんやりとした青い人形が現われる。 敵か味方かもわからず剣は構えたまま、そのぼんやりがはっきりするまで待った。 「……タ……カハ……」 どうも、そのぼんやりはゆっくり蠢きながら"タカハシ"と名前を呼んでいるようだった。 しかし魔物の罠かも知れず、まだ油断は出来ない。 「タカハシ…… 俺だ…………」 聞き覚えのある声に、姿形がはっきりとしてくる。 まさかと思い、ここにきて身体がブルッと一つ、震えた。 「テリー!」 「ああ。タカハシ、久しぶりだ」 ぼんやりとしているけれどそれは紛れも無くテリー。 こんな世界でどうしているのかと思えば、こうして目の前に現われる。 これまでどこに隠れていたんだと、どうやってここにきたんだと、無事だったのかと、たくさんの思いが溢れそうになる。 「すまん、タカハシ。俺もよくはわからずここにいるんだが、まず話させてくれ。 俺はルビス様にお前のことを聞いたんだ。そしてお前が眠っている間に静寂の玉をよくわからない場所へ収めてきた。 そうして今、お前がここにいる…… 俺は成功したんだな」 「そうだったのか…… 俺は無事戻ってそれからいろいろあって…… 今、簡単には話せそうも無いが、再会できて嬉しいよ」 「いろいろは、落ち着いたら話そうじゃないか。しかしどうやら俺はとんでもない場所へ現われたみたいだな。 なんで俺がここにいるのかタカハシ。お前知っているか」 「ああ。俺はこの崖に掛けるマジャスティスを待っていたんだ。 そうしたらテリーが現われた。もしかして、マジャスティスを使えるのか」 ぼんやりしたテリーが肯き、巨大な崖に向かって両の手を上げる。 しばらくの間を共に行動し戦ってきた友だけに、必要な事など言葉少なくとも伝わった。 ごうごうと魔物が再び襲い来る中で永い詠唱を始める。 「タカハシ、すまん! マジャスティスは詠唱が長い。魔物を任せたい!」 次々と襲う魔物相手に奇跡の剣を最大限に払い、魔物をドサバサと倒していく。 その間、詠唱の合間にテリーが話しかけた。 「単身修行の最中、カルベローナという寂れた町へ行ったんだ。そうしたらそこの長が、お前たちのことを話すじゃないか」 テリーへ食指を動かす魔物をバサリと切る。 が、魔物が触れたテリーは霧のようにフワフワとするばかりで、ぼんやりのままだった。 それは、この場所に実体が無いことを示していた。 「そこで、お前たちが探しているというこのマジャスティスの事を聞いたんだ。それから俺は、必死で探したよ。 もしかしたらお前たちが既に見つけているかもしれないのにな。その時は何も考えなかった。 で、いつかは忘れたがやっとの事で小さな盗賊団を見つけ、聞き込んだら持っていたというわけだ」 ここで魔物が途切れる。 一先ずは終わったようだ。 「もう少しで発動する。お前を探して姉を探して…… メイという娘は残念だったな…… いまさらだろうが、あまり気に病むんじゃないぞ」 「ありがとう。大丈夫だよ。吹っ切れたんだ、いろいろあって。 城が見えたら一緒に行こうじゃないか。約束した通り、一緒に魔王を倒そう!」 「ああ…… いくぞ……!」 テリーの身体からが、手の先から、青と白の輝く光が発せられる。 やがて眩しく一点へ集まり少しの間ぎゅうぎゅうとなった後、魔法名を叫ぶ。 「マジャスティス!!」 崖へ放たれた魔法が大きな網となりその一体を覆い隠し、ひゅんひゅんと音を立てながら見えない何かを剥ぎ取っていく。 テリーはその間物も言わずただ両手を挙げ集中している。 やがて青白がざあっと引き離された後に、居を構える探し続けた城が姿を現した。 洋風の複雑な出で立ちは見るものを圧倒しその不気味さはこの世の物とは思えない。 魔王に似つかわしい、邪悪な城だった。 「恐ろしいな……」 思わずこぼれる平凡な意見は、まったく当たり前だった。 正面には巨大な門が待ち構え、簡単には侵入出来そうにも無い。 さすがに少しばかり後ろへ下がりたくなったが、こうして現れた以上は進まなければならない。 終わりはもう、すぐ目の前にあるのだから。 テリーは詠唱を終え、少しばかり疲れていた。 肩を落とし安心しているようにも見える。 「ふぅ。この魔法はこれまで一回しか練習したことが無いんだ。 うまくいって良かったよ。これで俺の役目は終わりだな」 「何言ってるんだ。これから一緒に入って魔王を倒すんだよ」 「いいや。悪いがそれは出来そうも無いんだ」 そういうテリーの身体は、ぼんやりが更に薄くなり始めている。 ゆっくりと、それでも急速に透明な空気に混ざり込んでいくかのように。 「おい。嘘だろう。せっかく再会できたのに、これから一緒に戦うんだろう!」 「俺もそうしたいさ。だがどうやらこれが、俺の役目だったんだな。肉体がないのもそのためだろう。 ルビス様に頂いた最後の力ってのは、この事も含んでいたんだな。力も無くなりつつある……」 「待ってくれ! まだ話が!」 「会えて良かったよ…… 時が来ればまた……──」 すぅーっと、青い凛とした色が消えてなくなる。 魔物の気配も音も匂いも無く、地鳴りのような大気の咆哮だけが身体を揺らす。 話したいことは山ほど在った。 聞きたいこともうんと在った。 だがもう、叶わない。 そうするべき友は、この暗い空気と混ざって消えてしまったのだから。 結局、束の間の喜びはやはり束の間で、目の前を覆う忌々しい城と全ての元凶である魔王だけが残っていた。 ●魔王の失敗 マジャスティスによって暴かれた魔王の城は、たった二色で説明できる。 黒と白── その二色でのみ構成されていた。 複雑な外観も巨大な門も全てが白黒で、これが闇夜であったならまず見つけることは不可能だろう。 それというのも全体の黒が、大気中の明るさによってその輪郭のみを白く浮き立たせていたからだ。 崖にみせかけ暴かれてもなお、ひっそりと堂々と目付かないよう注意された建物。 それがこの魔王の城だった。 門へ手を掛けるとぞわぞわとした、大量の魔物の気配が感じられる。 おそらくここを開ければ城周辺にいた魔物全てが集まっていることだろう。 奇跡の剣を握りなおし一つ二つ腹へ力を込める。 大変な力が必要だろうと思っていた門は、あっけなく雲をおすように軽くぎぎぎと口を開ける。 開いた口へ頭をぐいと突っ込むとやはり、大量の魔物が息を殺し待っていた。 門の間がいったいなんなのかわからないくらいにひしめき合い、俺の姿を確認したというのにまだ動かない。 奇跡の剣をさっと構え、お互いの切っ掛けを待っている。 「ゆけ! お前たち!」 大小のびっしりとした黒い塊がどこからか聞こえた声に反応し、叫びとも囁きともとれない音をたてながら一斉に襲ってくる。 数は数十、数百か── もうとにかく目に付く魔物を間髪いれず、ほぼその場に足止めされた状態で倒し続けた。 ガスガスゴツゴツとした音とともに魔物が、目の前後ろ左右にばったり倒れていく。 倒れたそばから屍を乗り越え新たな魔物が襲い掛かる。 その魔物を倒しているうちに、先に倒れた魔物がきらきらと消えていく。 そうして床が見えたところへ再び、大小の黒い魔物が俺へと跳びかかる。 そんなことを繰り返しわかった事は、床が赤だということだけだった。 やがて、床の赤が目立って見えるようになり、魔物の数も急激に減ってくる。 俺もここまで戦ってきてそれなりに戦い方も解っている。 一振りで一匹を相手にしていたのでは、この場合分が悪い。 一振りに続けてもう一太刀、二太刀と続けるのだ。 そうなると必然的に跳ねる事となり強く踏ん張ることが出来ないから、一撃で仕留められない魔物が出てくる。 辛うじた魔物がやっと立ち上がり、別の方向を向いた俺の身体へ武器を打ち付けてくる。 ほぼ囲まれている状態だから、手が間に合わずどうしても全部は避けられない。 奇跡の剣で回復しながらだというのに、そうしたせいで傷は無くならなかった。 個々の魔物自体はどうという事も無いのだが、こうやってまとめて無秩序にこられるとさすがに狼狽する。 「ベギラゴンがあれば」 メイのとの連携を思い出し悔やむが、悔やんだところでどうしようもない。 ざわざわとする魔物たちを一心不乱になぎ倒す。 中には手ごわいモノもいて魔法を使って攻撃をしたりする。 そういうやつから真っ先に倒していった。 奥に居る場合は前列の魔物を踏み越えていくものだから、踏まれたほうは堪らないだろう。 なにせ一斉に踏んだ本人めがけ大勢の魔物が攻撃してくるのだ。 足元の魔物も巻き添えを食って同士討ちにあう。 そうやって徐々にごわごわする魔物たちを斬り払っていき、ようやく門の向こう側をなんの邪魔者も無く見渡すことが出来た。 そこは箱のような広間で、いくつかの扉しか目立つものが無い。 戦いで必死だったため気付かなかったが、ランタンのようなものが無数に天井や壁に設置され城内は明るい。 ここでもやはり壁は黒く、白の変わりに床が赤になっている。 その赤に目がなれた頃、床の一部がゆっくり持ち上がり床色をした鎧の魔物が姿を現した。 「私の名はサタンジェネラル。ただ一人残った魔王様の側近だ。 お前たち人間のしぶとさ、とくと見させてもらった」 「残る一人か。まぁ、俺は側近がいくつ居るかなんて知らなかったが」 「お前は強い。城内の魔物は全て今倒されてしまった。おそらく私も一つで殺されてしまうのだろう。 だが、魔王様の命のため向かわなければならぬ」 サタンジェネラルが長い矛を向け、突進してくる。 側近だというからには並みの魔物とは違うのだろうがそれでも、あっさりとした最後を迎える。 先ほどの戦いですっかり身体の温まった俺の動きに、サタンジェネラルはどうしてもついていけない。 がおんと、重たい金属同士のぶつかる音とともに、魔物の胴が大きく欠けた。 「ぐッ…… お前を生かしておいたのは、魔王様の失敗であると…… 今ならはっきり……」 サタンジェネラルの言った意味はわからないが、かまけている時間は無い。 あの扉を進めばきっと魔王がいて何もかもが終わる。 少し疲労はしたが、身体の傷はたいした事の無い掠り傷のようなものだ。 迷いなどはとうに捨て、奥へと続くであろう正面の扉をくぐり足早に階段を駆け上がる。 ●対峙 扉の奥にある真っ直ぐで不気味なレリーフの階段を、何段駆け上っただろう。 果たして本当に終わりがあるのかさえわからなくなるほど、長い距離と時間を駆けている。 先が真っ暗で何も見えないせいもあるとは思うが、実際にはたいした間ではなかったのかもしれない。 良くない気持ちは、持たなかった。 魔王を倒せば全ては元の通りになるという、精霊達の言葉があったからだ。 トルネコもテリーもルビスも、メイだって── 俺がうまくやればみんながまた元の、平穏な暮らしに戻ることが出来るのだと考えれば、一気に気力が充実してくる。 俺も全く帰れないというわけではないらしいから、とにかくやるしかなかった。 気が付くとどうやら奥の間へと続く入り口を見つけた。 薄く黒い壁をくりぬいた、更に漆黒の穴。 これまでとは明らかに違った気配と、べとつく圧迫感。 あれからますます強大に成ったと感じ取れる。 いよいよ覚悟を決め入り口をくぐり見渡すが一切何も見えない。 「我が元へ、よくぞきた。待ち侘びたぞ」 なんの予兆も無くボボッとたいまつが激しい炎を焚きあげ、奥の間全てをまぶしく照らす。 浮かび上がる王の間と、どんと玉座へ腰掛ける巨大で強大な魔王ゾーマがついに現われる。 「さあ来るがよい、異世界の若者よ。 貴様がいったい何処から来て何が出来るというのか未だ謎だが、ルビスの遣いであることに違いは無い。 どうであろうと貴様が生き残る事などありはしないのだ」 玉座の魔王は禍々しい波動を飛び散らせ、ざっと目の前へ降り立つ。 その自信に満ちた態度と表情は、俺の力など簡単に捻じ曲げてみせるといわんばかりだ。 「貴様にいうことなど何も無い…… 互いの全力を尽くし存在を賭けようではないか!」 ぐわっと広げられた魔王の手から強烈な波動が襲い掛かる。 とっさに剣を盾にするが目に見えない衝撃などというこの攻撃は、どんなに強固なものへ身を隠そうとも通り抜けてしまう。 「くそっ!」 突然始まった魔王との、この世界では最後になるだろう戦い。 まずはとにかく、邪神の像を破壊しなくてはならない。 魔王に注意しつつ周りを見渡すと、予想に反して邪悪な気配を持つ像はいくつも並べられていた。 形は全部違うとはいえ、これではまったく区別が出来ない。 面倒だが一つずつ気付かれないよう、隙を見て破壊していくしかないだろう。 渾身の力で奇跡の剣を振るい、魔王へ斬りかかる。 ざくっとした感触と共に、魔王の身体へ小さな斬り傷が出来た。 魔王は防御などせず、立ち尽くし俺の剣を受けていた。 「ほう。なかなか…… 力を付けた様だ。 もっと力を見せろ! 粉微塵に刻んでやろう!」 魔王の爪がごうと襲い来る。 すれすれにかわし剣を振るうが、片手で受け止められる。 すぐさま後退し、今度は太刀筋を変え斬る。 手ごたえはあるが、全く魔王に怯む様子が無い。 追う様に発する波動に身体が一瞬動きを止める。 奇跡の剣のおかげで回復できるとはいえ、これを続けざまに喰らってはさすがにもたない。 隙を与えないため剣を衝きたてるがこれもかわされてしまう。 流れるように二の太刀と体を動かしようやく切先が当たる。 と── ほぼ同時に魔王の豪腕に激しくなぎ倒されてしまった。 あまりの衝撃に息も意識も詰まり、身体のあちこちが悲鳴を上げる。 「う…… こ、ここまでとは……」 力の差があるのはわかっていたし覚悟は出来ていたはずだった。 だが、たった一撃がこんなにもこの肉体を傷つける。 ふらふら立ち上がる俺を少し離れた位置から見下ろし、魔王はあざ笑う。 「フハハハ! しょせん、お前たちなどこの程度なのだ。 ルビスの最大限の力をもってして、このお前の姿。 今の私に敵うわけも無い。私には世界の力があるのだからな!」 甘かった。 今の攻防は全力だったはずなのに。 そもそもが、戦ってはいけなかったんだ。 像を破壊するだけでよかった── はずなのに。 近付くことも、触ることなど到底出来そうに無い歴然とした力。 どうしていいのかがまったくわからず、ただなすすべも無く。 ●真の力 懸命だった。 そうに違いなかったはずだ。 俺の最大限とは、この程度だったのか。 「貴様はよくやっている。 私の攻撃にもう数時間耐えているではないか。褒めてやろう!」 左手がぐしゃりと嫌な音を立て、自由が利かなくなる。 魔王に掴まれ握りつぶされたのだ。 なぎ倒され状況を悟ってからこれまでずっと、こうして痛めつけられるだけだった。 「ぐあ……! あ……!」 どうする事も出来なかった。 邪神の像と思われる物は偶然を装い派手に吹っ飛び、既に三つほど破壊している。 だが魔王はまったく焦る事も無く堂々としているし、真の力といったものも発揮されていない。 像はまだ六つもある。本物がどれなのかがさっぱり知れず、けれど途方にくれる暇も無く。 全部を吹き飛ばされる度に破壊していたのでは、到底身が持たない。 疲労も傷も、限界を迎えようとしている。 左手も両の足も、深く傷つきまともには動かせない。 よろよろと立ち上がり、残った右手で剣を構えた。 「そろそろお仕舞いにするか。私も忙しい身でな。 これから新たに邪悪な世界を九つ創らねばならない」 魔王の手にガシリと首をつかまれ、高々と持ち上げられる。 首を絞められる格好となり、だんだんと頬が熱く酸素と血流が不足していくのがわかる。 あるはずのない無数の泡のようなものが、ぱちぱちと耳元で破裂していく。 細胞とかそういうものが潰れていっているのだろうか。 そうして魔王はきっと、そんな俺の命がしぼんでいくさまをニヤニヤと楽しんでいるに違いなかった。 もう、だめだ。 俺の力では、足りなかったんだ。 神々の見込み違いだったという事か…… 「フフフ…… 滅び際の命というものはいつ見ても美しいものだな。 喜ぶがいい、あの娘の元へ送ってやろう。我が体内で我が力となるがいい!」 この瞬間メイの顔が頭をかすめ、無傷の右腕が条件反射的に剣を魔王の腹へ深々と突き刺していた。 魔王は小さな呻きと同時に床へ俺を身体ごと叩き付け、幾つか跳ねた身体はずるずると床を引き摺ったのち壁とぶつかり、ぐったりとそのままになる。 本当に最後の力だったし痛みや疲労と壊れた身体は、どうやっても動かすことが出来なくなっていた。 「ちっ…… もう動けぬ身でやってくれたな。油断したがこの程度の傷、邪神の像を使えば一瞬で治癒できる。 足掻いても無駄だと、いい加減悟ったほうが安らかに死ねるというものだ」 魔王がゆっくり近付いてくる。 俺はだが、その視線の先に気付いた。 魔王は治癒しようと邪神の像に向かうと言ったのだから、進む先には…… もうろうとする頭でどうにか目線を返すと、そこに一体の像があった。 見ただけでは判別できなかったが、間近で感じるこの像の邪悪さは他を圧倒している。 「ああ……! これが……」 すぐ目の前にある、俺の破壊すべき目標。 剣は叩き付けられた際に手放し、はるか向こうに放り投げられている。 素手ではとても破壊する事など出来ず、仮に投げられた剣が利き手に握られていようと、この状態では最早破壊など不可能だった。 どうしようもなく、破壊の手段など何も持たなかったのだ。 「それが貴様の探していた邪神の像だ。気付いていたよ。 なにしろ貴様は、わざと大袈裟に像へぶつかっていた。 滑稽だな。私はわかっていて二度三度と像の近くへ投げたのだから」 「……俺は、ただお前のお遊びに付き合っていただけだと、言うのか……」 「ようやくまともに喋ったか。その通りだ。 貴様は私の積年の怒りをぶつける対象でしかなかった。 完全な力で完璧に圧倒されるためだけに、ノコノコ私の前に姿を現した。 決まっていたのだよ、こうなる事はすでに──」 突然、胸に激痛が走る。 魔王の攻撃かと思ったが一瞬見えたその表情は、何か別なものに驚いていた。 あまりの痛みに気を失いかける間際、すぐ目の前が真っ白な光に包まれ、真っ直ぐな光が像を貫いた。 陶器ではない、別の激しい音をがらがらさせながら崩れる邪心の像。 胸から飛び出した真っ直ぐな光はやがて四方へ散り、何かへ形を変えてゆく。 身体も気力も全てが尽き、ここへきてどういうわけか何かが起こった。 この現象が真の力なのだとしたら、これからどうなるというのだろう。 俺は痛みの中やがて気を失い、何が起こったのかを考える事も出来なくなった。 ●魔王の最後 誰かに揺られ、はっと目を覚ます。 痛みはだいぶ無くなり、身体の感覚もさっきよりは回復している。 だが目が、まるではっきり見えなかった。 「大丈夫かい。ベホマをかけたのだけれど、ここまでしか回復させてあげられなかった」 「だ、だれだ。目が、見えない」 「目が見えないのは、魔王と戦っていたからベホマがだいぶ遅くなってしまったからだよ。 君はかなり危険な状態だったのだけど、今はもう大丈夫だからね。 視力はすぐ治るから、君はここにいて!」 どれほどの間、気絶してしまったのだろう。 たくさんの人間の気配を感じる。 剣のぶつかる音や魔法が発生する音に肉を切り裂く音、そういった衝撃音と誰かの会話だけが今得られる情報だった。 「よし! このまま一気に!」 「ガアアア! 貴様らごときが私の邪魔をするな!!」 視力がようやくはっきりとしてくる。 最初に見えたのは叫ぶ魔王だ。 だが、最後に見た魔王とはまるで違う、すっかり老いてしまいボロボロになっている姿だった。 その周りを囲う、傷付きながらも果敢に攻める八人── 見たことも無い戦い方と剣技を使い、強力であろう魔法を放ち、完璧であろう補助と回復魔法を駆使し、確実に魔王を追い詰めている。 ゴオン、ガアンとぶつかり合う衝撃が離れたこちらにまで伝わり、身体がビリビリと痺れた。 剣で舞い、激しい一閃をぶつけ確実に、魔王は追い詰められていく。 俺が、全力で戦ってもまったく歯が立たなかったというのに、この男達はいったいどれほど強いというのか。 「これで終わりだ!!」 ガツンと、バンダナの男が強烈な一撃を加える。 怯んだ魔王へ男達の連続攻撃が容赦なく打ち込まれ、武器の重なった後にはガクリと崩れた魔王の姿。 はぁはぁとだらしなく息切れを起こし鮮血を噴出させ、老け込んだその顔は悪夢の形相だ。 「ぐう…… 私は、力を取り込む毎に、世界の成り立ちを知った。 ついに世界の記憶を知ったとき、わが運命も決まったかに、思えた。 闇は光に、倒されなければならず、お互いはそれだけの理由で存在する。 私には無意味に思えた関係の循環。それをまず、破壊するべきだと考えた。 絶大な、命の力を持つ源を断ち切れば、もしやと…… だが、成らなかったようだ……」 どうにか生き長らえている魔王の台詞に、鎧の男が静かに語る。 「理屈も何も無く、ただそうなると決まっていただけだ。 邪悪は必ず正義に敗れる。これが我々の常識であり世界の秩序なんだと思う」 「……我々が存在する意味とは、いったいなんだというのだ。それならば存在などさせねば、いい……」 「もう残された時間が無い。止めを刺させてもらう。 ……お前の言うこともわからない事も無いが、やっぱり俺達はこの世界に存在する生命なんだ」 ざっと、オリハルコンによって刎ねられる魔王の首。 あっけなく、求めてきた瞬間が知らない人間の手によって終わってしまう。 魔王の巨大で汚れた亡骸がぶあっと黒い煙を吐き、消えて無くなった。 そのすぐ横で、それぞれ回復魔法を掛けたり休憩したり傷を癒す男達が居る。 彼らの表情を見れば、相当激しい戦いだった事がわかった。 俺はまるで関わりが無いように、離れた場所で相変わらず天井だけを見つめた。 「君が僕らをここまで連れてきてくれたんだね」 代表したように、背の低い素朴な少年が傍へ来て礼を言う。 俺には何がなんだかわからないから「はあ」としか答え様が無かった。 だから聞いた。 「あの。あんた達は一体……」 「そっか。全部を聞いていないんだね。じゃあ、知っている事を説明してあげるよ。 君は、いや僕らはずっと君の身体の中で邪神の像が破壊されるまで待っていたんだ。 神様達が決めたことだからどうしても別の事では出られなくて…… 君もだいぶ苦労したのに、最後を持って行っちゃったみたいでごめんね」 「ずっと、見ていたのか…… 複雑な気持ちだよ。 しかし強いな。俺にはまったく歯が立たなかった魔王を、倒してしまうのだから」 「大丈夫! 余計な物とかなんというか、僕らに関係のない場面は見てやしないから! それに魔王に勝てたのは、邪神の像を破壊したおかげで魔王の力が急速に衰えていったからだよ。 君がいなければ、絶対に勝つことなんか出来なかった」 「そうか…… で、結局ルビスが言っていた真の力っていうのは、あんた達の事なのか」 「うん。僕らはギリギリまで力を温存していなくちゃならなかったんだ。 けど、君が危なかったし邪神の像も特定できたからって、早めに開放されたんだ。 思ったより力を付けた魔王のせいで出るためにはかなり大きな力が必要になったけれど、精霊達のおかげで出られたんだよ」 「あの光はそういうわけか。……俺は、あんた達を運ぶための器だったという事なんだな。 それより最初から自分達で邪神の像を探して壊し、魔王を倒してしまったほうが早かったんじゃないのか」 「うーん。そうもいかなかったんだ。 僕らは自力でここへ辿り着くほど、長い時間をこの世界では過ごせないから。 ほら──」 少年が指差す先の、七人の身体が細かい光の粒に包まれ始めていた。 もちろん少年も同じだった。 「そろそろ時間が来たよ。僕らが出来るのは、ここまで。 あとは神様か何かが、全部元に戻してくれるはずだよ。 いつか、また会えるといいね!」 少年が戻り八人同士でもしばらく何かを話しているようだったが、一人がすうっと伸びた光のように消え、また一人と消え、間も無く誰もいなくなった。 残ったのは中途半端に回復した俺と、がらんどうの静かな城内。 気味が悪いから外へ出ようとしたが、どうしたことか身体にまったく力が入らず動けないから、起こってきたこれまでを考えるしかなかった。 ●異世界の人間 ルビスや精霊は、肝心な事柄を正確には教えてくれなかった。 なぜそうしたのかはわからないが、俺が知ることで不都合があったのだろうか。 ……不都合だったのだろう。 おそらく、正直に全部を俺に話してしまえば、単なる運び屋として命を掛けるなんてまっぴらだと抵抗したかもしれない。 それとも暴走して余計なことをしてしまったかもしれない。 きっとこの世界の住人ならば、勇者の為に働くわけだからと積極的に動き、喜ぶに違いない。 だが俺は別の世界の人間で、この世界のそんな常識は通用しない。 元の世界へ戻るという大前提はあるのだが、それでも素直にそうですかとは、たぶん言えなかった。 そんな状態だったら、此処まで自分を鍛えることなんてしなかっただろう。 ふと魔王を思い出す。 あんなに苦しめられた魔王だったが、最後は実に生命らしい言葉を残していった。 どういう気持ちで観念したのだろうと思うと、不思議と少し同情した。 世界の秩序として邪悪は必ず倒されると決められているなら、邪悪を倒すのも勇者である事が世界の秩序であり、俺に倒されてはならない。 そう考えれば役目の意味も良くわかる。 地上では強い力で魔物を倒し続けたが、それは勇者達を魔王と戦わせるまでの安全な入れ物である必要があってのこと。 この世界の人間では出来ない器の役割を担い、それを無事に完遂し、魔王討伐に直接手を下す事は無かった。 光と一緒に飛び出したらしい八人は、勇者だったんだろう。 長年の生活と魔王を打ち倒すといった目的を持たされ、すっかりこの世界の住人のつもりになっていた。 全部が終わってこんな事に気付くなんて本当に虚しくなるが── 「最初から最後まで俺は、異世界の人間だったんだ」 ……そういえば、これからどうなるのだろう。誰も何もそれだけは教えてくれなかった。 このままここで朽ちてしまうのか。 急に心細くなり周りを見渡すと、あったはずの床や壁や天井がすっかり無くなり、理解の出来ない空間が広がっていた。 見えているのだけれど、そこはいったいなんなのか。 立体なのか平面なのか、丸か四角か、物かそうではないのか、そんな単純な事も理解できなかった。 徐々に不明な空間が周りの物質を飲み込んで行き、近付いてくる。 精霊達の言っていた世界の破壊というやつなのか。 不明な空間へ身体が落ち込みさらさらと肉体が崩れていく感触。 砂より微細な光でも空気でもなく、単なる現象として失われる肉体。 静かに厳かに。 全部、終わったんだ…… 『……このまま帰す事は出来ません。いのちの源は今今、あなたをこの世界の人間として記憶へ刻みました。 あなたに最後の役目を与えます。元の世界へ戻りこの世界を忘れる前に、世界の復活を住人として見届けるのです』 見届ける……── ●再生された世界 世界はすっかり再生された。 邪悪な存在が現われ、それを打ち倒す勇者によってもたらされる平和。 幾つかの物語が紡がれ、確かな安定が続いている。 各世界の魔王が討伐されてからも、魔物は依然として数多く存在し人間と敵対した。 だがそれも世界の秩序で、消えることの無い関係は遥かな年月を重ねていく。 タカハシと共にあった仲間は、再生されたそれぞれの世界で元の通り暮らした。 三つ目の世界で、トルネコは妻であるネネと武器屋を繁栄させた。 六つ目の世界ではテリーが旅の剣士として、ミレーユは占い師の職に就きそれぞれの道を暮らした。 メイは、四つ目の世界でどこかの城の姫だと偽ったり誘拐されたりもしたが、仲間と共に芸の旅を元気に続けた。 誰一人としてあの不安定で邪悪な世界を知らずに。 八つ目の世界に平穏がもたらされた後、いくつの年光が過ぎただろうか。 九つ目の世界が新たに創られた。 新たな世界にはまだ勇者は現われず人々は不安な毎日を送るがきっと、勇者によって平和が取り戻されるだろう。 それから更に多くの月日が流れ、それぞれの世界が、やがていのちを一周する頃── ●ある村の老人 ある世界の小さな村で、目立たない高齢な店主が生活に役立つ道具を売っている。 長年、いつから暮らしていたのかはわからないが、村の誰からもその穏やかな店主はとても好かれていた。 「じいさん。あんたもいい加減、一人身で居るのも飽きたろう」 買い物に来た青年が言う。 だけれど店主はそんなことなどまったく気にも留めない様子で返答する。 「いいや、ピピン。 ワシはもうずいぶん一人で生きたんだし、それだけで十分満足なんじゃ」 「ふうん。そんなもんなのかな。 俺なんかいつまでたっても、こうやって女房がいたって女っ気は欲しいもんだがな」 「そりゃあ、ほれ。お前はまだ若いのだから。 それに、なんだかワシにはこの先が長く長く、何かをこうして待たなきゃならん気がしているんじゃよ。 だから今の世はこのままで良い」 「あんたは時々よくわからない事を言うよな。まあいいや。 もし必要なら言ってくれ。じゃあな、タカハシじいさん!」 青年が居なくなり店はまた、静けさを取り戻す。 元来がひっそりとした平和なこの村だから、それは平常通り日常なのだ。 「ワシはまたいつか、時折踊るこの胸の内を精一杯に過ごす。 だから今は、こうして静かにしているんだよ」 誰に言うでもなくポツリとこぼし、穏やかな顔はまるで遠い将来を楽しみにしているよう。 それから数年が経った頃、タカハシ老人は静かにいのちの源へと還元された。 当たり前に時世を迎えるために。 ●少年の約束 遠くまで見渡せる緑の平原で、二人の少年が仲良く遊んでいる。 「おういトルネコ! こっちにこいよ、珍しい枝が生えているよ!」 「はぁはぁ…… 待ってくれよ~、タカハシ。 僕は君みたいに身軽じゃないんだから」 「はは。僕は君みたいに道具に詳しくないんだから、おあいこだよ」 「ふぅ。そうは言ってもなぁ。あ、これは珍しいよ。 世界樹といって、大きな樹の子供なんだ。 きっと大きくなったら立派な葉っぱをつけるんだ」 「そうかぁ。さすがに物知りだね」 「この樹には言い伝えがあるんだよ。なんでも、葉を持っていれば奇跡を見られるって」 「ふぅん。じゃあさ、この樹は二人の内緒にしようよ。 大きくなったら僕とトルネコで葉っぱを持って、奇跡を見よう!」 「うん! 約束だよ!」 「お、あっちにも何かあるよ! 行こう!」 「待ってくれよ~、タカハシー!」 向こうに見つけたものは何だろう。 無邪気な少年達は無垢な心を持ち、遠い未来で約束を果たす。 ●兄弟の旅 悠久の時は、現象を自由な発端で生み出していく。 広大な砂丘を三人の兄弟達が旅をしていた。 「テリー。お前はこういった事が好きなんだろうが、俺は全く興味もないし恐ろしいんだ」 「なぁタカハシ。俺はお前がもっと強くなる予感がして仕方が無い」 「またそれか。何度言ったらわかるのか、魔物を斬るなんてしたくないんだよ。 姉さん。テリーに言ってやってもらえないかな」 長い金色の髪を持つ美しい女が、二人の男に呆れて言う。 「あなた達。こないだだって、雷鳴の剣を手に入れるため危険な旅をしたじゃない。 心配で仕方の無い私の身にもなってほしいのよ。 タカハシだって嫌だと言いながらここまで着いて来ているのだし。 斬るのが嫌みたいだけれど、私が見る限りあなたは筋がいいし、残念ながら率先して戦っているように伺えるわ」 「そんな。それが姉の言葉かなミレーユ。俺は好きでこんな事しやしない。 スライムだって怖くってしょうがないんだ」 「はは! タカハシ、お前は面白いことをいつも普通に言ってくれるな! もういい加減に弱気を言うのはよせ。自分をわかっていないのはお前だけだよ、なぁ姉さん」 「いいわ、どうだってもう。とにかく私はあなた達が心配だから着いて行くけれど、危なくなったら絶対に助けなさい」 「ああ。大丈夫だよミレーユ。だって兄弟で一番恐ろしいのは……」 テリーが慌てて何か合図をする。 だが、すでに手遅れだったようでタカハシの周りに魔法の気配が浮かび上がる。 「ご、ごめん! ごめんなさい!」 「また言ったわね、それを…… 今度は容赦しないから!」 「あちっ! 待った! ベギラマはひどいよミレーユ!」 その光景に笑い転げるテリー。 そのうちタカハシがあんまり上手に逃げ回るものだから、しびれを切らし発せられたメラがテリーに直撃し砂が舞う。 まったく平和な、この丈夫な兄弟にとってはささいな喧嘩だった。 ●回帰 円を描き続く時間の奥行き。 同じ所ではなく進みながら描くからバネのような形状となり、縦軸では必然的に重なる点が発生する。 どれほど隔てただろう。幾度と無く重なり続けた点は、ずれた機会を徐々に合わせていく。 それが必然のことであったように、ついに繰り返してきた重なりの、完全な一致を迎える。 フレノールの外にある小さな丘へ出掛けることにした。 その場所は特別で、物思いに耽ったりする時は必ず訪れている。 ふらふら歩く町中は、休日らしく思い思いに過ごす人で賑わう。 丘へ着くと先客がいた。 よりにもよっていつも座る窪みににちょこんとしていたから、新たな場所を探さなくてはいけない。 なんだか落ち着かずうろうろしていると声をかけられ、咄嗟の事だったからうまく返事が出来なかった。 「こんにちは」 「あ、あー」 「もしかして、ここはあなたの場所だったかな」 「いや、大丈夫だよ。俺は適当な場所を探して座るから」 「そう」 適当な場所といっても小さな丘だから、座る女のすぐ側辺りに腰を降ろす。 結構な間を、お互い遠くを見たまま何も話さなかった。 静かな風だけが草木をゆったりさわさわとさせる。 女が突然、フフッと笑い出す。 どうも俺の事で笑ったらしいから、なぜと声をかけた。 「だって、声をかけたらあーあーなんて変な返事するものだから」 「そりゃそうだよ。突然声をかけられたら誰だってああなると思うよ」 「そうかな。そういうところ、あんまり変わってないみたい。あの頃と」 返事が、返せなかった。 止まった時間は容易く壊れるものであったりするけれど、その切っ掛けがなかなか見つからない。 「元気そうだね、タカハシ」 「……メイも変わらないな。あの頃と」 「これは奇跡なのかな」 「いいや。たぶんルビスだと思う。 それにしても── 長かった。だけどようやく、ここまで辿り着いたよ」 「うん。長かったね」 二人はそれぞれのこれまでとあの世界の記憶を持ち、再開した。 こうなるまで、何回始まりと終わりを過ごしたかわからない。 この瞬間がいつまでも永劫に続けばいいと、そう思う。 「ねえ。どう過ごしてきたのか、聞かせてくれる?」 「ん、そうだなあ。 ……テリーって憶えてるか? 俺と一緒にフィッシュベルにいた青い服の。 実はそのテリーと兄弟になっちゃってさ……──」 暖かな日差しに柔らかい風がすうすうと吹いていた。 これまで同様、この世界での長い人生が再び一旦の休みを貰うまで、風に乗る声は絶える事無く吹き続ける。 ●最後の記憶 最後に憶えているのは旅をした皆と同じ村に暮らし、異世界の人間であるヨウイチとの出会いだ。 それが、最後の記憶。 遠く赤く、こうして見える光は朝陽だろう。 目を開けばきっと、剣も魔法も魔物もいない現実の世界が待っている。 けれど、しばらくは充実したあの日々の余韻を楽しみたい。 瞼を閉じている間はまだ消える事の無い、あの世界の住人なのだから── おしまい。