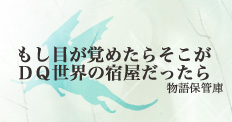
「モンスター使いとはモンスターの邪悪な心を打ち払うことができる存在なのじゃ。」 僕はモンスター爺さんからモンスター使いの講義を受けていた。 「これはある一族だけが持つ力だと言われておる。」 「ふーん。お師匠様ってその一族の人なんだね。」 「おそらくはな。モンスターを仲間にできる者は目が違うのじゃよ。」 そうなんだ。今度お師匠様の目をじっくり見てみよう。 「あ、それじゃ僕がいくら頑張ってもモンスター使いにはなれないってこと?」 「現状ではそうじゃな。じゃが案ずることはないぞ。」 「何かいい方法があるの?」 「モンスター使いが仲間にしたモンスターの世話をすることをやればよいのじゃ。」 それってモンスター爺さんのことだよね。僕が今やってることでもあるけど。 ん? 「あー! 今気づいたけど僕のやってることってモンスター爺さん見習いじゃないか!」 そうだよ。何で気づかなかったんだろう。 「これモンスター使い見習いじゃないよ! 僕が爺さん見習いっておかしいよ!」 「落ち着け。モンスター使いもモンスター爺さんも似たようなもんじゃ。」 全然違うよぉ…… 「それにな。その一族の者でなくてもモンスターを仲間にする方法はある。」 「え、それを早く言ってよ! どうすればいいの?」 「魔王がいなくなればよいのじゃよ。魔物が邪悪な心を持ったのは魔王の影響じゃ。」 「魔王っていうのがいなくなればモンスターが大人しくなって仲間にできるの?」 「ま、そういうことじゃな。」 「魔王って地獄の帝王のことなの?」 「いや、魔王は地獄の帝王復活を利用して魔物たちを統率しておるだけなのじゃ。」 うーん。ややこしいね。 「かつて地獄の帝王が復活し勇者が誕生したときも魔王が現れたというぞ。」 「どんな奴だったのかな。」 「何でも1度は勇者を倒したといわれている。」 「ええー! 勇者様やられちゃったの?」 「それは勇者の影武者だったらしい。あるいはキツネに化かされただけなんて話もある。」 え、キツネに化かされたの? 「もしかして魔王って結構お茶目な人なのかな。」 「いや怖い存在じゃ。恐ろしいモンスターたちの親玉なんじゃからな。」 「モンスターっ恐ろしくないよ。いい子ばっかりだもん。」 「ここにいる者はそうじゃ。じゃが野生のモンスターは恐ろしい存在なのじゃ。」 ホイミンやガンドフを見ているととてもそうは思えないんだよね。 「何度も口を酸っぱくして言っておるが野生の魔物がいる町の外に出てはいかんぞ。」 「大丈夫だよ。僕インドア派だからね。それにしてもさ……」 「なんじゃ?」 「口を酸っぱくしてって妊娠したみたいだよね。」 「妊婦は酸っぱいものが欲しくなるだけで口が酸っぱくなるわけじゃないわい。」 あ、そういえばそうだね。 「まったく。どうやったら爺さんが出産するというのじゃ。」 「うーん。口から卵を産んで。」 それって口が酸っぱくなりそうだよね。 「わしゃ化け物か。わしゃモンスター爺さんであってモンスターではないぞ。」 「はーい分かってます。本気で言ってるわけじゃないよ。」 「本気で言っていたらわしゃ泣くぞ。」 とにかく僕はモンスターの世話を頑張ることにするよ。モンスター使い見習いとして。 「よし、こんなもんかな。」 僕はイナッツさんとモンスターたちの部屋を掃除していた。 「ご苦労様。きれいになったわね。」 「うん。でもちょっとにおいが気になるよね。」 ここって地下室だからモンスターのにおいが篭るんだよね。 「ねえ、いいものがあるわ。あれよ。」 そう言うとイナッツさんは小さな陶器の瓶を指さした。 「ここに花やハーブのエキスを入れて香り楽しむのよ。」 「アロマセロピーみたいだね!」 「このエキスを布に染み込ませて体を拭けば香水代わりにもなるわよ。」 そうなんだ。 「でも食べたら毒だから口に入れちゃ駄目よ。」 「はーい。口を酸っぱくして言わなくても大丈夫だよ。」 小さな瓶はほのかにいい香りをしてたてている。 「あ、これを使えばガンドフの獣臭さも取れるかな。」 僕は瓶のふたを開けた。これを布に染み込ませて体を拭けばいいね。 「えーと、ただの布きれがどこかにあったよね。」 どこだっけ? 「あったあった。」 いやー探しちゃったよ。布は部屋の外に干してあった。 「あれ、ホイミン?」 僕がモンスター部屋に戻るとホイミンが倒れていた。 「ホイミン! ホイミンってば!」 「ホイミンは大丈夫?」 「峠は越えた。もう心配はないぞ。今眠ったところじゃ。」 ホイミンは間違ってアロマのエキスを飲んじゃったらしい。 でも無事で良かった。本当に良かった。 ごめんねホイミン。僕の不注意で大変な目にあわせちゃって。 僕はその夜ずっとホイミンの看病をした。 次の日。お師匠様が来た。タイミング悪いよ…… お師匠様は今まで砂漠の中にあるお城にいたんだって。 どうしよう。僕怒られちゃうかな。 でも、仕方ないよね。僕が悪いんだもん…… ううう……お師匠様怖い顔してる気がする。 お師匠様の目をじっくり見ようと思っていたけど、とてもできないよ。 「今日は大事な話があるんだ。」 何だろう? ひょっとして「お前は破門だ!」って言われちゃうのかな…… 僕が心配している中お師匠様は重い口を開いた。 「もう、お師匠様っていうのをやめて欲しいんだ。」 ああああ……やっぱりそうなんだ。 お師匠様、僕を捨てないでよー。 僕この世界じゃほかに頼る人がいないんだ。 もし元の世界に帰れなかったら僕は、僕は…… 「あの、あの……これから、僕は、どうしたら……」 「これからはさ、お父さんって呼んで欲しいんだ。」 「え?」 「いやさ、やっぱりお父さんがいないのは寂しいんじゃないかと思ってね。」 「ええと……」 「トモノリが元の世界に帰るまで、お父さんの代わりをさせてほしいんだ。」 「私のことはお母さんって呼んでね。」 目の前の夫婦は2人ともにっこり微笑んでいる。 「トモノリいつもモンスターの世話をしてくれて、ありがとう。」 「でも僕、ホイミンを危ない目にあわせちゃって……」 「ちょっと不注意だったけど、そのあと一晩中つきっきりで看病してくれたんだよね。」 「だけど僕きっとホイミンに嫌われちゃったよ……」 「そうかな? おーいサイモン。」 お師匠様が呼ぶとサイモンがホイミンをつれてやってきた。 「ホイミン! もう起き上がっても大丈夫なの?」 「ああ、もうすっかりよくなったようだな。」 ホイミンはふわふわと僕のほうに近づいてくる。 「やれやれ、ホイミンは俺よりトモノリのそばほうがいいのか。」 サイモンがちょっと寂しそうに言った。 「これでもホイミンに嫌われてると思うのかな?」 嫌われちゃうかと思ったけど、そうならなくて良かった。 「ね、お父さんとお母さんって呼ぶこと考えておいて。」 お師匠様と奥さんがお父さんとお母さんになってくれる。 かっこいいお父さんと綺麗なお母さん。 この世界にいる間だけだけど。 ……でも、僕いつになったら帰れるんだろう。 こっちにお父さんとお母さんができたから、もうしばらくいてもいいけどね。 もし、このままお師匠様に子供が生まれなかったら本当の子供になっちゃおうかな。 そのためにはもっといい子にならなくちゃね。 そんなことを考えているとサイモンが頼みごとをしてきた。 「おーいトモノリ。煙草を買ってきて欲しいんだ。」 「煙草? お使いだね。いいよ。僕、行くよ。」 「お、ずいぶん素直だな。」 いい子になるって決めたんだもん。 「でもさ、煙草はやめたほうがいいよ。」 「そう思ってもやめられないものなのだ。それに鎧だから健康の心配ない。」 それもそうだね。あれ、でも、そもそもどうやって煙草を吸っているんだろう? 「だが我が身を案じることがないわけじゃないぞ。」 「そうなの?」 「戦闘中ロッキーが攻撃を食らうとメガンテしないかとひやひやする。」 「そうなんだ。ロッキー大丈夫かな。」 「うむ。あれは鎧の身にとっても心臓に悪い。」 「大変だよね。あ、それじゃ僕、お使いに行ってくるよ。」 「そうだ。ついでにレモンを買ってきてくれないか。」 「レモン? 体でも磨くの?」 「違う違う。奥方様が、何か酸っぱいものを食べたいと言っておられたのだ。」 「ねえ、お師匠様。僕やっぱりお師匠様のことお師匠様って呼ぶよ。」 「お父さんって呼ぶのは嫌かい?」 「なんだかさ、やっぱり恥ずかしいよ。」 「そっか。可愛い子供ができると思っていたんだけどちょっと残念だね。」 「あなた、無理を言っては駄目よ。」 「ごめんね。お師匠様。おかあさ……おかみさん!」 「え、おかみさん?」 「そう、お師匠様の奥さんだからおかみさんって呼ぶことにしたんだ。」 子供になれなくってごめんなさい。でもさ、お師匠様の願いは……すぐに叶うよ。 「そうだお師匠様。サイモンとロッキー置いていってくれないかな。」 「え? でも……」 「わがまま言ってごめんなさい。でも、一緒にいたいんだ。」 「分かった。そのかわりしっかり面倒見てね。」 お師匠様はサイモンとロッキーを置いてまた旅に出た。 今度はグランバニアって言うお師匠様のお父さんに関係があるを土地を目指すんだって。 「いいのか? 本当は2人の子供になりたかったんじゃないのか?」 サイモンが話しかけてくる。 「いいんだ……」 これでよかったんだよね。 「ところでだ。俺はお前の嫌いな煙草を吸うしロッキーはいっしょにいると心臓に悪い。」 サイモンは不思議そうに尋ねてくる。 「俺とロッキーを置いていけってのは何か意味があるのか?」 「それはね、サイモンは煙草を吸うしロッキーは心臓に悪いからだよ。」 お師匠様自分の奥さんの妊娠に気づいてないみたいだった。 今の僕にできることってこれくらいだ。 僕がおかみさんの妊娠を知ったときはまるで刺されたみたいな衝撃を受けた。 お師匠様が知ったときはどんな顔をするんだろう。 「ま、確かにグランバニアへ連れて行くのにロッキーは危険だな。」 「え? どういうこと。」 「グランバニアへ行くには険しい山道を越えていかねばならんのだ。」 「えええ! だ、大丈夫かな?」 僕は奥さんを置いていくように言うべきだったのかもしれない。 「何かあったらどうしよう……」 お師匠様もおかみさんもお腹の赤ちゃんも、どうか無事にグランバニアに着きますように。