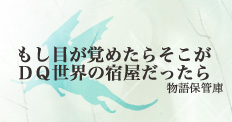
あのジプシー姉妹、誰に似てるって叶姉妹に似てるんだ。 別に顔は似てないがゴーマンな姉と少し控えめな妹というあたりが。 いやあ、納得がいったよね。(いかない?だったらゴメン!) だけど俺は現状に納得がいかないんだ。 何がって? 藤岡弘ばりに洞窟の探検に赴いた俺たちを待っていたのは、いきなりの落とし穴だった事さ!そりゃテンションもおかしくなるYO! ばか、ばか、まんこ!いきなり一人ぼっちとか無理すぎだろ!?最初のダンジョンにしては難易度高いじゃないか!! きっかけはフジテレビだった。 違う、これは今はもう遥か遠い世界のキャッチフレーズだ。 そうきっかけは、あのホフマンとかいうDQNのせいだ。 あいつが素直に俺たちに馬車を献上していればこんな事には…って、まあ考えてみると、譲ってくれって方が無理がある気がするんだが。 この『裏切りの洞窟』の中に、『しんじるこころ』という名の宝石があるらしい。 馬小屋で眼を覚まし、テンションの低いままぼーっとしている間にいつのまにかそれを取りに行く事になっていた。 今思い返せば、洞窟なんぞにこないで宿屋で待っていれば良かったのに…。 いや、それも叶わぬ願いか。どうせ荷物もちに担ぎ出されただろう。 兎に角、今は何とか脱出を目指さなければならない。 ひたり、ひたり。 己の足音がまるで自分のものである気がしない。 ぽたり、ぽたり。 何処かで水滴が落ちているのか。暗闇の中、松明の明かりで床を照らしてみると僅かに濡れているようである。 そういえば、洞窟に来るまでに橋を渡った気がする。 周りを水が走っているのだとしたら――嫌な感じだ。 水、というのにどうしてこうも不安になるのだろう。俺のゲーム知識では水は大抵優しいウンディーネの結晶だというのに。 溺死のイメージ。溺れるという事。何処かで記憶に刻み込まれているのだろうか。 俺は何気なく腰に手をやった。そこには、ソフィアのお下がりの銅製の剣がある。 それだけで、少しだけ気が楽になった。 手探りで進むうちに、やがて昇り階段らしきものを発見した。 俺は慎重に、気配と足音を俺なりに消した上で足を進める。 ――キィン。 澄んだ音が響く。 階段を抜けた先の広間には、ソフィアと、叶姉妹が烈しい剣戟を響かせていた。 「――な!?」 溜まらず、驚きの声を上げてしまう。これが俺の経験の浅さだろうか。 切り結んでいたソフィアとミネアは直接俺の方を見ず、マーニャのみがその鋭い視線をちらりと俺に向けた。 えぇい、バレちまっちゃあしょうがない。 「何――やってんの」 その何とも間の抜けた問い。それに、まずマーニャが答えた。 「良かった、心配していたのよ。――それが、私たちにも解らないのよ。 あの後、ソフィアともはぐれてしまってようやく見つけたと思ったら、突然後ろから……」 心配?心配だと?胡散臭SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!! ぷんぷん臭うぜええええええええええええええとまあジョジョっぽい感想を抱く。 「ソフィアさんは何者かに魔法をかけられているのかもしれません。 幻惑呪文か混乱呪文か…兎に角、動きを止めないことには調べることもままならなくて…」 と、ミネア。 妹の方は――電波ゆんゆんだが、受信している時以外はとても優しかった。 ソフィアの事を本当に心配しているように思える。 「――――――――……………………」 そして、彼女は喋らない。言葉を紡ぐ事ができない。 一瞬だけ視線が絡む。だが、彼女はすぐにそれを外し、今一度――大剣を構えた。 はがねのつるぎ。 エンドールで俺が家に帰る手段を模索していた時に、ボンモールへと足を伸ばした彼女が手に入れた剣呑な光を反射する武器。 そう、それは銅の剣などとは比べ物にならぬ程の『武器』であった。『武器』は、容易に全てを傷つけ犯し、殺す。 ソフィアはそんなものを――同じ人間に、共に行こうと言ってくれた仲間に、振るおうとしているのだ――。 そんな事は、させたくないと。胸の奥で感じた。 だから俺は腰に差した銅の剣を抜いた。鋼の剣と比べると、余りに脆弱な武器だったけれど。 だけど脆弱だから、少なくとも彼女を傷つけずに済むと思った。 一歩、二歩と足を進める。 彼女を傷つけずに済んだとしても、俺は傷ついてもしかすると死んじゃうかもなあとも考える。 恐怖に足が震えた。それでも、がくがくと震える足を無理やりに前に出した。 三歩、四歩。 俺は姉妹を背に、ソフィアと対峙する。 そうして、こんな事は止めてくれ、と頼んだ。 ソフィアが伏せていた顔を上げる。 瞳が、強烈な光を放っていた。俺の心身はその光芒に飲み込まれる。 涙を決して浮かべるものかという、彼女の決死の意思が俺を貫く。 唇が動く。少女のものにしては鮮やかに朱い。 彼女は言葉を紡げない。だけど、その時俺には何故か彼女の言葉が聴こえた気がした。 読唇術なんて気の利いた技術なんて持ち合わせている訳が無い。そんなものは漫画の中でしか出来なくて、俺は現実の通りに鬱になるくらい無力で。 だから俺が出来た事は唯(たった)一つ。――彼女にはきっと確信があるのだ。だからソフィアを、信じる。 ソフィアが身体を弓のように引き絞り、剣を突きの形に構える。 一足飛びで俺との距離が詰まる。俺の身体ごと貫かんとするかのように――だが刀身は俺の身体を避けて――体当たりをするかのように俺へと身体を浴びせかけた。 ドン、と俺の身体は弾かれる。その反動で、ソフィアもまた逆方向に身体を流す。 後ろからミネアが繰り出した槍の穂先は、今まで俺が居た空間を通過した。迷い無く繰り出された穂先は、本来ならば俺ごとソフィアを貫いていたのだろう。 ――ズス、ン。 大剣がミネアの柔らかい身体を貫いた。それは、俺が今迄聞いてきたどんな音にも似ていなくて。 思ったよりも乾いた音だと思ったのも束の間、ぐちゅり、と臓腑が軋む音が響いた。 その時、既に俺の身体は動いていた。 ソフィアが剣を引き抜く前に、首を掻っ切ろうとマーニャが伸びた爪を閃かせる。 俺は無我夢中で剣を振るった。 スパッと、何かを薄く切り裂いたような、そんな手応え。 だがそれはそんな生易しいものではなく。 マーニャは首から噴水のように紅い水を撒き散らし、その場に崩れた。 ……会心の一撃、というヤツだろうか?は、ハハ――。 バカな事を考えて意識を逸らそうとした努力も虚しく、俺は突如訪れた嘔吐感に従い胃の中のものを吐き出してしまう。 「――うぐっ、おぇぇぇぇ……」 ソフィアが背中を摩ってくれる。明らかに年下の娘に対して、余りに恥ずかしく情けない姿なのだが、そんな事を考えられる余裕はとても無かった。 殺した。殺してしまったのだ。人間を。仲間を――。 此処は、裏切りの洞窟。 こうやって、あのホフマンという男も…。 瞳に涙が浮かんできてしまう。だが、決してそれを零すまいと必死で堪えた。 どんなに人を嫌おうと、殺してしまいたいと思ったとしても、そんな事は絶対に実行してはならない事だと解っていた。 今でも昔と変わらず解っているのに、今の俺は解っているなんておこがましくてとても言えない。 どうして、と。何故、が。ぐるぐると渦巻く中で、それでもまだ神父に診せれば間に合うんじゃないかという考えに至ったのは僥倖なのだろうか。 慌てて身体を起こそうとした、その時。ソフィアが、俺の背で指を動かしているのが解った。 何度も何度も、同じ軌道を描く。少しして、彼女が何をしているのか理解した。 『大丈夫』 自然と、深い呼吸が為される。 そしてもう一度マーニャとミネアの死体を見てみると、そこには彼女たちの屍は無く。 恐ろしげな顔をした小鬼(と、言ってもホンモノの鬼を見た事は無いのだが、俺が持っていた鬼のイメージに近かった)のようなモノが二匹、斃れているだけだった。 考えてみれば、そうだ。俺の一撃なんかでマーニャが死んでしまう訳がない。 それもまた、それはそれで身震いが起きるし、この手で何かを殺した、という事実は変わらないのだが。 『信じて』 何を――何を信じろと言うのか。 ソフィアを信じろと言うのか。 マーニャとミネアはこんな簡単に斃れたりはしない。俺に斃されたりする彼女たちが本物である筈が無い。 それが、マーニャとミネアを信じるという事なのか。 だが、それらは余りに俺に都合が良すぎる――独善的な信頼のように感じられる。 信じるとは――なんなんだ?依存とは違うのか? 俺はさっき何を信じた?マーニャとミネアの言葉を聴いてソフィアと対峙し、そうしてソフィアの声無き声を聞き、彼女を信じた。 ソフィアを信じて、マーニャとミネアを信じなかった。 しかし、あのマーニャとミネアは本物の彼女たちじゃなかったんだ。 ――だからといってマーニャとミネアを信じなかった訳じゃないなんて言うのは――卑怯じゃないのか。 答えは、無い。 ループしかける思考の渦を、頭を振ることで辺りに散らす。 こんなところで立ち止まっている訳にはいかない。今は、それに縋るしかなかった。 洞窟の探査を続ける中で、俺たちは再度、姉妹を見つけた。 彼女たちは俺たちの偽者に襲われたらしく警戒しており、ソフィアに質問を投げかけていた。 ソフィアは首を縦横に振り、危なげなく解答し、姉妹の信を得た。俺については、ソフィアが大丈夫だと言うのなら大丈夫だろう、という事らしい。 信頼したものである。だが、それは俺も同じで、ソフィアが大丈夫だと言うのなら、この姉妹は本物だと思えた。 俺は、ソフィアを信じたのだろう。そうして、マーニャとミネアも同じく。 ――では、ソフィアは何を信じたのだろうか? マーニャとミネアの姿をした魔物と迷い無く対峙したソフィア。 本物のマーニャとミネアを見つけた時は、姉妹とは対照的にまるで警戒した素振りも見せなかったソフィア。 洞窟の最深部にて。 俺たちは、『しんじるこころ』と呼ばれる宝石を手に入れた。 その宝石は確かに、視る者の心に優しく触れるような光を放っている気がした。 帰り道。 ミネアが荷物を少し持ってくれ、腰にホイミ(俺も習っている治療魔法)をかけてくれた。ミネアに言われて、マーニャもぶつくさ言いながら手伝ってくれた。 ソフィアは元より、手伝ってくれている。 彼女の胸元には、『しんじるこころ』が光っていた。 その光を見ていると、何かが頭に流れ込んでくる気がした。それは知識というよりも、理解そのものに近い。 きっと、どれもが真なのだ。 信じる、という行為。その在り方はそのどれもが正しいんだ。 マーニャとミネアの強さを信じるのも真ならば、彼女たちの言葉を信じるのも間違っていないんだ。 例えばそれが偽者の騙りで、その後悲劇が待っていたとしても、信じた行為そのものは究極的に偽である事は無い。 勿論、盲目的なのもダメだし嘘に騙されてしまってはダメだ。 だからこそ、常に客観的な視線を心がけなければならないし、騙されない為には相応の知識と齟齬を見抜く直感もまた必要になる。 俺はあの時マーニャへの違和感とソフィアの視線を受け理屈は解らずとも、ソフィアの意思と確信を信じた。 俺がそれ以上の確信を持てた時は、こちらが信じてもらう側に立つ。それが、盲目的な信頼や依存とは違う、信じるという行為。 そうしてそれと同時に発生する――覚悟、というものの存在をも『しんじるこころ』が照らしてくれたのだろうか。 ……信じること自体は、既に出来ていた。足りなかったのは、ソレなのだろう。……いや、そう。俺に足りないのはきっと、その覚悟だけでは無い……。 俺はソフィアだけじゃなく少しずつでも、マーニャとミネアの事をより知る事で、より信じたいと思っている自分が居る事に気がついた。 そうしてそれこそが、『信じる』という事の始まりなのだとも。 HP:32 MP:5 Eてつのまえかけ Eパンツ Eどうのつるぎ