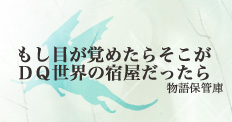
従者の病を治す為、薬草を求めて出立したサントハイム王国王女、アリーナ。 これだけを聞くと中々感動的なストーリーだが、大体において伝わる話とその実態には齟齬がある事が多い。 今回のケースでは齟齬とまではいかないかもしれないが、いずれにしても――彼女は、この旅を心から楽しんでいた。 彼女にとってみれば、随分と長い間待ち焦がれ、何度も無理やりにその手に掴み取ろうとして叶わなかった願い。 念願の一人旅、である。 ミントスの町から東へ進み、ソレッタの村へ。 道中で現れる魔物をたった一人で撃破し、見事に辿り着いて見せた。 彼女は美しいと言うよりはまだ愛らしい外見であったが、それよりなにより、生気に溢れたその姿が見る者を魅了して止まない。 サントハイム王家には代々、魔力の強い者、それだけに留まらず特殊な力を発揮する者が産まれて来たが、 残念ながらアリーナ姫に魔術の素養は皆無であった。 だが――はたまた、それ故にか。 ただひたすらに強かった。それに加えて未だ成長途中だというのがおかしいのだ。 人は、実のところそれほど無力な存在では無い。 子供や老人でなければ、例えミネアの言う導かれし者では無かったとしても、そこそこに戦えるものは少なからず居る。 しかし、人と魔物を比べた時に、どうしても超えられない壁があるのもまた、事実であった。 そしてアリーナ姫は――導かれし者達の中でも抜群の、それは時に勇者すら超えかねない――才と器を備えた少女なのだ。 現段階の実力で言うならば、噂に名高いバトランドの王宮戦士辺りならば互角かそれ以上の者もいるかもしれないが、 こと、身体的・肉体的な素質に関して言うならばアリーナに勝るものはいないと言っても過言では無い。 さて、そんなお姫様であったが、ソレッタの村で手に入る筈だったパデキアが既に絶滅して久しい、と言うのには少し困った。 幸いなことにこういう場合に備え、冷気の満ちる洞窟の奥深くに種を残してあるらしいのだが、 そこは現在魔物の巣になっており、村の人間では取りに行く事ができないらしい。 ――なんとお誂え向きのシチュエーションだろう。 勇んだ彼女は早速、洞窟へ向かおうとしたのだが、珍しくも一つの思案をする。 果たして、己一人で目的を達成する事ができるだろうか、と。 これが『魔物の棲家になっている洞窟を探検する』だとか『洞窟に篭もって修行をする』だとかなら、 一人で行って戻ってくるという行為自体に意味も出てくるのだが、今回はあくまでパデキアの種を入手するのが最優先、手段と目的が入れ替わることがあってはならない。 これはブライがいつも口を酸っぱくして語る教えの一つであった。老人がこの場にいたなら感激したかもしれない。 アリーナはブライに甘えている所があるのか、老人が居る場合だと事の外彼の教えを無視して無茶をしたがる傾向があったので。 さて、となるとやはり一人では難しいかもしれない。 事は一刻を争うので悠長に何度も赴く訳にはいかないし、そうなると治癒の術が使えるものは必須である。 魔物を蹴散らして進むのが探査する際に効率的である以上、戦士の頭数もあるに越した事は無い。 洞窟に入る必要があると事前に解っていればミントスで募る手もあったのだろうが――そうすると、今度は道中の速度が下がっただろうし、いずれにしても過ぎてしまった事をごちゃごちゃと言っても仕方が無いと気持ちを切り替える。 そして、アリーナはたまたまソレッタに逗留していた世界を救う旅をしているらしい戦士一行の手を借りる事にした。 だが――。 「――逃げ足、速いわねぇ」 ふぅ、と軽くぼやく。 そもそも、鍵のかかった扉をアリーナが蹴破った時点でどうもビクビクしているようだった。 最初は若い娘の頼みだからかへらへらと二つ返事で同行を受けてくれた彼らであったが、 アリーナの予想外の実力と、洞窟内の魔物の強さとに完全に恐れ戦いてしまい――逃げ出してしまったのである。 「ま、良っか。こうなった以上は私が一人でパデキア手に入れてみせるわ…!」 逆境に燃えるタイプなのか、苦境に立たされた後でも彼女の炎は消える所かより燃え盛るばかりであった。 「あ~!苛々する~!なんなのこの床は~!」 ダン! 余りに燃え盛ってしまった炎は捌け口を求め、今回は床に霧散する。 アリーナは洞窟の仕掛けに非常に苦労していた。 どうしても床が滑ってしまって目の前にある階段に辿り着けないのだ。 こういう場合はいつもクリフトやブライが彼女を宥めると共に、仕掛けを解いてきたものなのだが――。 つきん、と痛んだ拳を唇に当てる。 魔物との連戦の際に負った怪我だ。もう少しで、薬草も尽きてしまう――。 その焦燥が、隙を生んでしまう。 突如横合いから巻き起こった大気の変動にアリーナは対処し切れず身体中を切り刻まれた。 「うあ!?痛った~って――ブライ!?」 いいや、それはコンジャラーである。 コンジャラーと間違えたなどとあの老人が聞いたら最早嘆き悲しむ所の騒ぎでは無いかもしれない。 この間違い自体は良くあるネタなのだが、少し今回は間が悪かった。 アリーナの一瞬の躊躇が、彼女の命を縮める――。 「せぁ!!」 鋭い剣撃がコンジャラーの首を跳ね飛ばす。 頭と泣き別れになった胴体は、ぐらぐらと揺らいだ後仰向けに倒れた。 アリーナは一瞬何が起こったのか理解できなかったが、目の前に立つ人影に対し反射的に構えを取っていた。 ――その、禍々しきは鎧兜。 首から足の先までを覆う全身鎧(フル・プレート)に、顔はフルフェイスの兜を被っている為表情が見えない。 だが、さまよう鎧とも違う――確かに、肉体の気配がするのだ。 それは先ほどの気合の声であったり、息遣いであったり視線であったり。そういった有機的なものをアリーナは本能で感じ取った。 鎧は血のついた剣を横に払う。それが合図であったかのように、アリーナは飛び掛った。 顔を目掛けた飛び蹴り――そして、本命は首元への刺突。 彼女の手には無数の魔物を屠り続けてきた鉄製の鉤爪が光っている。 蹴りがかわされ、続く爪撃。手応えは――無い。いや、浅い。 鉄板の上を滑った感覚。避けられた――そう認識する前に、鎧はアリーナの足を掴み、軽々と放り投げていた。 「――くっ!」 空中で軽業師のような身軽さを発揮し体勢を立て直し着地する。 今一度――そう、アリーナが構え直したときには、鎧は剣を鞘に収めてしまっていた。 「待て。俺は、君と戦う気は無い」 鎧から男の声が漏れる。 アリーナは不服だった。今の攻防は、悔しいがあちらが一本取ったと言わざるを得ない。 身体がまだ動く、いや例え動かずとも、負けっ放しなど冗談では無い――。 「この洞窟にパデキアがあると聞いた。君は、知らないかな」 だが。目の前の男は、強い。 強者は強者を知るように、アリーナは心と身体、その両方で眼前の鎧――それは、まるで騎士のように見える――を認めていた。 この男と戦って勝てるだろうか。薬を手に入れクリフトに届ける事ができるだろうか。 ――できない事は無い。だが難しい、と判ずる。 「解らないわ。私も、探しに来たんだけどね」 「そうか……」 手を口元にあて、思案する騎士。 その人間的な仕草を見て、アリーナはやはりこの男は魔物の類では無いなと感じた。 鎧兜は相変わらず嫌な気配を漂わせていたけれど。 「ね。物は相談なんだけど。私と一緒にパデキアを探さない?」 「君と?」 「そう。貴方、中々強いようだし。お互い、足手まといになる事は無いと思うわ」 「…さっきのは、俺を試したという事か?」 声に不愉快さが混ざる。 ソレに対し、アリーナはあっけらかんと答えた。 「それもなくは無いけど、とりあえず私は相手が強そうなら戦ってみたいのよ。それだけ――ううん、実はもう一つあるけど、それは秘密」 その鎧兜の余りの邪悪さに、つい手が出た。 だが、流石にこれは余計だと思ったし、それにどうしてだかこの男の声音は――暖かいのだ。 闇と光の両方を内包したアンバランスさ、いやそれは実はアンバランスなどでは無いかもしれないが――不可思議なモノを感じる。 そうして、興味を持ったというのが正解に近いかもしれない。 「……そう、だな。それも良いかもしれない」 逡巡の後、騎士の応えが返る。 こうして、姫君と騎士は共同戦線を張る事になったが、それはよくある英雄譚とはかけ離れたものだった。 洞窟の中を縦横無尽に駆け回り、身体で魔物を屠って行く姫君に、追随し彼女のフォローをいれながら、的確に障害を取り除く騎士。 それは傍目から見れば良いコンビに見えたかもしれないが、以前、滑る床には苦労していた。 「――待て。そこはさっき踏んだぞ」 「え?そうだっけ?じゃ、次はこっちね」 「だから待てと。そこは、見るからにダメそう――」 「え?あわわ…」 「えぇい、仕方の無い…」 意外と面倒見が良いのか苦労性なのか。 騎士もまた律儀に同じ床を滑る、が少し先ほどとは違うルートに焦りを見せた。 段々と近づいてくるのは、ぽっかりと口を空けた落とし穴だ。 「――!?」 騎士は落ちる瞬間、咄嗟に腕を伸ばしアリーナを抱え込む。 金属と床が烈しくぶつかり合う音。そして、無音。 アリーナは、恐る恐ると言った風に鎧の上で身体を起こした。 「……生きてる?私なら、着地できたのに……」 「……生きてはいるが、それを聞いて酷く落ち込みそうだ……」 ごほっと咳き込みながらも、ずるりと身体を引き摺り壁に寄りかかる。 アリーナも、その隣にちょこんとしゃがみ込んだ。 「少し、休憩させてくれ」 ふぅ、と軽く息を吐く。 そうして、暫しの沈黙が流れる。 居心地が悪い訳では無かったけれど、何かしら喋っても良いかしら、とアリーナは思った。 「ね。…デスピサロって、知ってる?」 ――デスピサロ。 その名前を聞いた瞬間に、騎士の様子が豹変した。 手は握りこまれ、ぶるぶると身体が震えているのが解る。 憎悪。焦燥。無力感。それらがない交ぜになったような――。 「知ってるの!?なら、教えて!私は――私は、ヤツに会わないと……!」 「――何故、デスピサロに会わないとならないんだ?」 今度はアリーナが黙る番だった。 時間のみが過ぎて行く。それは大した長さでは無かった筈なのに、二人にとっては永劫にすら近く感じられた。 「…良いわ。全部教えてあげる。私の名前は――サントハイム王女、アリーナ――」 城を抜け出したこと、エンドールの武術大会で優勝したこと、蛻の殻のようになっていた城に凱旋したこと――。 王を含めた城内の皆を探す旅に出たこと、旅の途中で魔物が活発に動き出しているとの噂を耳にしたこと、遠くバトランドではピサロの手先と名乗るモノが子供狩りをしていたらしいこと――。 それが、エンドールの武術大会に出場し、参加者を殺しまわっていた不気味な男、デスピサロと符合したこと。 「――そう、か」 少女が語り終えるまで、騎士は沈黙を守っていた。 再び流れる沈黙。アリーナは、身じろぎもせず、じっと待った。 「……今は、まだ、教えられない」 「どうして!?」 待った挙句の拒絶の言葉に、アリーナはいきり立った。 掴みかかるかのような勢いで、騎士に詰め寄る。だが、彼は憎らしいほどに冷静だった。 「――デスピサロは、俺よりも遥かに強いからだ。君をむざむざ死なせたくない」 アリーナの瞳に炎が宿る。ぎり、と歯が軋む音が響いた。 余りの悔しさに、涙が出そうになる。だが、この場で、この状況でかんしゃくを起こす程子供にもなれなかった。 騎士は、静かに手をかざし、アリーナに上位治癒(ベホイミ)を施した。 「俺は未だ身体が動かない。――お前も、急いでいるんだろう?」 アリーナの脳裏に今もまだ、病床で苦しんでいるであろうクリフトの顔が思い浮かぶ。 「――いいわ。だけど、私が戻るまで此処で待ってなさいよ!?」 飛び跳ねるように駆けて行く少女を見送り、騎士は小さく嘆息した。 真っ直ぐな少女だ。お供が常に傍にいてくれた、というのも大きいのだろうか。 ――あの少女からは怨嗟、憎悪などが全く視えなかった。今の己には、存在さえすればはっきり視える筈なのに。 それらが無い筈は無いのに――それ以上の、何かで覆われているかのよう。 似たような境遇にありながら、違うものだなと感じる。 だがそれは決して嘆く事では無い筈である。――それとも、そう思うことで自分を肯定したいのだろうか。どうしようもなく愚かな己を。 結局、パデキアの種は見つからなかった。 アリーナがそれらしき場所に到達した時には、既に箱の中身は空っぽだったらしい。 騎士はがっくりと肩を落とす少女に、せめて町まで送っていこうと伝える。 瞬間転移(ルーラ)で、一気にミントスへと戻った二人は、町の入り口で暫し見詰め合った。 そう長い時を共にした訳ではない。 だが、何かお互いに感ずるものがあったのか。 「――助かったわ。ごめんね、パデキアを手に入れられなくて」 「気にするな。こっちはそれほど深刻な状況じゃない」 「そう――良かった、のかな?」 えへへ、と笑うアリーナであったが、騎士にはそれが明らかに無理をしていると解ったから。 だから最後の問いにはこう答えたのかもしれない。 「ねぇ。また、会える?」 「――ああ。会えるかもしれないな」 アリーナは嬉しそうに破顔した。 それは、少なからず少女の影を吹き飛ばす事に成功したようでもあった。 「うぅん、絶対に会うわ!数少ない手掛かりだもの!次に会う時には、貴方を圧倒してみせる!!そうしたら、ちゃんと喋ってもらうからね!!」 そうして、姫君と騎士はそれぞれ宿屋へ、隠れ里への帰路につく。 この二人が再度出会うその時は何時になるだろうか。