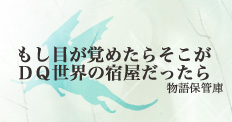
『あっ?パパスさん?パパスさんじゃないかい?』 船がゆっくりと離れていくのを見送りながら、俺は背中越しに男の声を聞いていた。 『いやあ、無事に帰ってきたんだねえ。よかったよかった。心配していたんですよ』 振り向くと、ただでさえ丸い顔を更にしわくちゃに丸めて男がパパスの肩に手を置いていた。懐かしそうに嬉しそうに、パパスが笑うとその手も上下に揺れる。 『わっはっは、痩せても枯れてもこのパパス、おいそれとは死ぬものか』 予想通りの台詞がパパスの笑い声に混ざり合って俺まで嬉しくなる。 こんな台詞普通使わねーよバッカじゃねーのウケルー とか思ってたテレビの前の俺、ちょっと死んでこい。 思い出話に花を咲かせる二人の横をすり抜けようとすると、パパスが顔を上げて『遠くまで行くんじゃないぞ』と叫ぶ。片手を挙げて了解の合図を送り俺はまず樽の調査に取り掛かった。 収穫は殆どなかったが、小さな手が幸いしてか突っ込んだ樽の隙間から小銭を拾った。大事にゴールド袋に滑り込ませる。 顔を上げると、風が海のにおいと草原のにおいを運んできて俺は大きく息を吸った。排気ガスに汚されていない空気なんて生まれて初めてだ。こんな風なら少しは救われるかもしれない。この世界に。 俺はこの先を知っている。何もかもを。 忘れていることはあっても、憶えていることはそれより遥かに多いはずだ。 死ぬ人も。生きる人も。 今までデジタルでしかなかった、空想でしかなかった世界が初めてはっきりと自分の中に重くのしかかる気がした。 夢だ。夢。誰が死のうと、殺そうと、全てはどうせ夢なんだから。 頭を振って不安を追いやって、俺は港の傍らの小さな小屋の扉を開けた。 さっきの男のおかみさんか。小太りの女が忙しなく小さな部屋の中を動き回っている。外から見ると粗末な小屋も中は綺麗に整えられていた。窓際には、一輪挿しから伸びたピンク色の花が申し訳なさそうに首を傾げている。 『あら、ぼうや今の船から降りたの?』 俺に気付いておかみさんが笑顔を向ける。子供相手の、屈託のない笑顔。 「うん。お父さんと一緒に」 素直な子供を演じて言葉を返すと、おかみさんは、 『そういえばねえ、ずーっと前にここから旅に出た人がいるのよ。ぼうやくらいの歳の小さな子と一緒にね。パパスさんは元気かしら。懐かしいわねえ』 小さなお客に頬をほころばせながら昔を懐かしむ眼差しで窓の向こうを見やる。 「それ、僕だよ。パパスお父さんと一緒に今船で来たんだ」 無邪気に聞こえるようにゆっくりと言葉を選びながら言うと、おかみさんはまあ、と声にならない声をあげて俺の顔をまじまじと見つめ、一層明るい笑顔を零した。 『ぼうやがあの時の・・・。じゃあパパスさん、無事に探し物は見つかったんだね。良かったねえ』 つられて微笑むと優しく俺の頭を撫で、おかみさんは俺にこんなものしかないけど、と言いながら飴玉を握らせてくれた。その手が暖かくて、俺はさっきの自分の考えを恥じた。 例え夢でも。いや、夢だからこそ。俺の夢の穏やかな日常を、この世界を壊そうとする奴を、俺は許しちゃいけないんじゃないか。 俺は勇者にはなれないかもしれない。けど、俺がこの世界を救おう。 あまりにもすんなりと、俺は誓いを立てた。ゲーム脳で良かった、感情移入はお手のものだ。この時ばかりは俺は自分の単純な脳みそに感謝した。 おかみさんに丁寧すぎるほど丁寧にお礼を言い、俺は改めて表に出た。相変わらず太陽は眩しく世界を照らしている。 パパスは埠頭で主人と話し込んでいる。俺は息を整えると、ゆっくりと港の出口へ向かった。 階段を上がる足が覚束ない。初めての戦闘だ。生まれて初めての、実際の戦闘。 大丈夫。パパスがすぐに駆けつけてくるのはわかっている。出口でもう一度深く呼吸をして俺は草原へと踏み出した。 青々とした低い草の中、申し訳程度に均された道を辿っていく。このまま寝転んで一休みしたら気持ちいいだろうけど周りはモンスターの巣窟のはずだ。低い草に紛れて、どこからスライムが襲ってくるとも知れない。スライムならまだいいけれど、他のもう少しでもレベルの高いモンスターに遭遇したら。 今現状を考えれば、スライム相手にも致命傷をもらいかねないのだ。 慎重に辺りを見回しながら、腰に巻きつけてあった木の棒を握り締める。後ろを振り返ると、まだ港からは数歩の距離しか離れていない。 戻ろうかと思考を巡らせた刹那、背後から甲高い鳴き声が聞こえた。動揺し思わずたたらを踏みながら振り向く。 つるんとした質感の、頭の飛び出た青い物体が、一、二、・・・三つ。両端に飛び出した目と大きく開かれた笑っているような口で辛うじて生き物だとわかる。 ―――来た。スライムだ。 ピキキ、と鳥の鳴くような声を発して右端の一匹が飛び跳ねた。とっさに身を硬くするが、右膝に鈍い痛みが走る。 ゼリー状だって聞いてたけど、結構硬いじゃねえか奴ら。 頭の片隅で冷静な俺が呟く。左端の奴がまた飛び跳ねるのを思い出したように木の棒で叩き落すと、スライムは地面で一回跳ねて体勢を立て直した。やはり今の俺には、スライムさえ強敵に違いない。警戒するように真ん中の奴が少し後ずさる。俺は息を呑む。 『サン!サン!大丈夫か!何やってる!』 後ろから不意に響いた怒号に俺はやっと安堵の溜息をついた。地面まで揺らすような足音を立てて、パパスが俺の元に駆け寄って来る。 『遠くへ行くなと言ったろう!全く』 俺を守るように立ちはだかるパパスの背中にも安堵がにじんでいるのを感じて、俺は思わずごめんなさい、と口にした。 パパスが二匹のスライムを切り伏す間に難を逃れた別のスライムに一発食らったが、最後は俺の一撃で三匹目のスライムも動かなくなった。パパスが振り向き、何か呟くとさっき受けた痛みが嘘みたいに引いていく。 ホイミ。初めて受けるパパスのホイミ。 幾度となく助けられてきたパパスのホイミ。 『お前にはまだ外は危険だ。今回はたまたま父さんが気付いたから良かったものの・・・ 気をつけるんだぞ』 諭すように言いながらパパスはスライムの亡骸を簡単に調べ始めた。つるりと反射する三つの青い死骸から慎重に何かを抜き取る。 『これはお前にやろう。初めてモンスターに勝ったごほうびだ。・・・良くやったな』 そういって笑顔で手渡されたのは、キラキラと光る三枚のコインだった。それを頷いて受け取り、ゴールド袋ではなく小さなポケットに大事に押し込むと、俺はパパスの背を追って歩き出した。 つかテメー外に出ないと話動かねえじゃねーかよ。 と片隅の俺が思ったけれど、それは心の奥にしまっておいた。 村はすぐそこだとパパスは言った。俺には途方もなく遠く長い道のりに思えた。幼い足は長旅に慣れているらしくすぐに疲労を感じることはなかったが、それでも村の輪郭が遠く 地平の向こうに見える頃には足の裏は痛み、ふくらはぎもパンパンに張っていた。 パパスは俺の手を握ったまま俺のペースに合わせて歩いている。それは心地好い安心感だった。けれど戦闘の一瞬、手が慎重に解かれるその瞬間だけは言いようのない不安が俺を襲った。 痛恨の一撃を食らったらお終いだ。死ぬことはないと解っているけれど、その一瞬の暗闇がどんなものかを想像すると無意識に膝が震えだす。 村のゲートをくぐるその時まで、不安は付き纏っていた。 午後の陽は傾き始めていた。刻々と伸びていく自分の影を追いながら、緑の合間に見え隠れする村の風景が少しずつ生気を増していく。 入り口のゲート脇の警備兵がこちらに気付き、一瞬の訝しげな表情を崩し、顔を輝かせた。 『パパスさん?パパスさんじゃないですか!戻られたんですね!』 満面の笑みで兵士がパパスに駆け寄る。今帰った、とパパスが言い終わらないうちに 『そうだ!皆に知らせなきゃ!皆に挨拶しなきゃ!パパスさん!』 とパパスの手を引いて村の中に駆け出す。パパスと繋いだままの手を強く引かれて、俺は慌てて歩調を合わせようと足を速めた。 『皆さん!みんな!パパスさんのお戻りですよ!』 村全体に響き渡るような大声で、兵士が叫ぶ。何事かと顔を出した住民達が、パパスの顔を認めると一斉に顔をほころばせるのが見えた。 老若男女。宿や商店の店員までもが嬉しそうにパパスの元へ駆け寄り、無事を喜び、俺の頭を撫でたり感慨深げに顔を覗き込んだりしていった。 影が傾いていく。 それぞれに挨拶を済ませ、話し足りない風の村人をなんとかそれぞれの持ち場へと戻し、パパスはゆっくりと、踏みしめるように村の奥へと向かった。 奥まった場所の、古ぼけた一軒家。質素だが手入れの行き届いた庭。その向こう、家の玄関先で小さなふたつの目いっぱいに涙を溜めて、喜びに歪んだ顔の太った男が深々と頭を下げた。 『旦那様。おかえりなさいませ』 『サンチョ。随分と待たせてすまなかったな』 その大きな右手を男の肩に乗せると、男の両目からぽろぽろと雫が零れ落ちた。 『ええ、ええ。旦那様。生きて戻られると信じてはおりましたが、この日をどれほどに待ち侘びたことか・・・』 最後は殆ど言葉にならなかった。深い皺の向こうに長い苦労と不安が垣間見えた気がして俺は、眉間が痛むのを感じて俯いた。 やっと部屋に落ち着いてもサンチョはひとしきり泣いて、ひとしきり喜びの言葉を口にしていた。パパスはひとつひとつに頷いて、苦労をかけたな、と一言だけ口にした。子供として掛ける言葉が見つからずただそれを眺めていると、階上から小さな足音が聞こえた。気がした。 『おじさま、お帰りになられたのね!お帰りなさい』 階段の手すりから顔を覗かせて、綺麗なブロンドを両耳の上で括った少女が弾けるように笑顔で階段を飛び降りた。着地でぐらつき、照れたように頬を赤らめる。 姿を見なくても解った。ビアンカだ。 『サンチョ、この子は』 『あたしの娘だよ。パパス、久し振りだねえ』 大きな体を億劫そうに揺らしながらパパスと同年輩の女がゆっくりと階段を下りて来て言う。 『おかみじゃないか、隣町の宿屋の。じゃあこの子はビアンカちゃんか。いや、大きくなって』 少女とおかみを見比べるようにぱちぱちと目を瞬き、パパスが驚きの混じった笑顔を浮かべる。 『じゃあダンカンも来ているのか?』 問いかけにおかみは困り笑顔を浮かべ、 『それがあの人ったら、病気で臥せっちまってね。ちょいとこっちまで薬を貰いに来たんだよ』 『折角なので寄っていただいたんですよ。旦那様も私も、お世話になっておりますので』 いつの間にかすっかり涙を拭いて、サンチョが口を割る。 おかみが椅子につくと同時に、隅でもじもじと足元を見ていたビアンカが俺の腕を小突いた。 『ねえ、上に行かない?大人の話って長くって』 こくんと頷くとビアンカはじゃあ行きましょ、と俺の手を取った。 今の俺と変わりない小さな手。その温かさになんだか俺は妙にほっとした。なんとなく、ゲームの中でやっと気を許せる相手を見つけた気がした。 思考が幼児化しているな、と気付く。ビアンカ―この幼い少女を同年代の相手と無意識に認識している。 感情移入もここまで来ると少し危うい気がして俺はほんの少し気を引き締めた。 本棚とベッドだけの小さな二階の部屋に上がると、ビアンカは周りを見回して『ここって何もないのよね』と洩らした。と、くるりと振り向き俺の両手を取って 『ね、あたしのこと覚えてる?前にうんとちっちゃい頃、会ってるんだから。でもあんたはもっとちっちゃいから、覚えてないかな』 にこにこと子供をあやすように語り掛ける。曖昧に頷くとふん、と溜息をついて 『あたしはあんたよりふたつも、お姉さんなんだからね?』 と両手を腰に当て、威張れる相手を見つけた幼子の小さな威厳に満ちた瞳で俺の目を真っ直ぐ見下ろす。 『そうだ、ご本を読んであげるわ。お姉さんだもの』 綺麗に編み込まれたブロンドを揺らしてビアンカは本棚に向き直った。『どれがいいかな』と口元に指を当てる。自分より僅かに身長の高い少女の隣について俺は読めもしない本の中から適当に「これ」と指差した。ビアンカの瞳が輝く。 『仕方ないわね。じゃあそれにしましょ』 大儀そうに分厚い本を抱えてベッドの上に開き置き、うつ伏せに寝転んでぽんぽん、と自分の隣を示す。やはり高く感じるベッドによじ登ると、俺は少女に倣って隣にうつ伏せた。ビアンカは満足そうに頬づえを付いて足を揺らし鮮やかな挿絵のページを繰っていく。 ビアンカが体を動かすたびにブロンドの一本一本がくすりと俺の頬を撫でる。 『そら・・・うーんと、そ、ら、に、・・・く、せし・・・難しいわ』 小さな額に皺を寄せてビアンカが整然と並んだ文字を追う。あまりに一生懸命な少女の姿に俺は思わず沸いてくる笑みを抑えた。 『ビアンカ、降りてらっしゃい!そろそろ戻りますよ』 押し黙って文字を追う最中、階下から聞こえた声にはっと顔を上げて、 『残念だわ、宿に帰らなきゃ。ご本はまた今度ね』 ほっとしたようにビアンカが笑う。本を閉じ小さな手を俺の額に重ねて、 『また遊びに来るわ。あんたも字を覚えるといいのに』 もう一度にっこりと笑うと、少女は本を抱えてベッドを降りていった。 本棚の隙間に分厚い本を押し込み階下へと降りていくビアンカの背中を見送ってから、俺は体を起こした。刹那、どすん、と大きな音がして階下から大人たちの笑い声が響く。 『ごめんなさいね、この子ったらもう』 笑うおかみさんの声を聞きながら階下を覗き込むと、階段の真下、尻餅をついたままの体勢でビアンカがけらけらと笑っていた。俺の視線に気付き照れ臭そうに唇だけでやっちゃった、と言うとひょい、と身軽に立ち上がる。 挨拶もそこそこに扉をくぐると、宿まで送ろうかと言うパパスの申し出を丁寧に断り二人は薄暗闇の中手を繋いで帰っていった。 階段の一番上に座り込んで暫く大人二人の会話に聞き耳を立てる。今までの旅のいきさつと、サンチョを気遣うパパスの言葉。特にこれと言って収穫はなく、立ち上がろうかと言うところで物音を聞きつけてパパスが口を開いた。 『なんだ、サン、まだ起きているのか?』 そっと立ち上がって階下に顔を出すと、サンチョが丁度腰を浮かせたところだった。 『ぼっちゃん、お疲れでしょう。今日はもうお休みになられますかな。旦那様、少しお待ちくださいね』 笑顔で俺を抱き上げ、ゆっくりと気遣いの速度で階段を上がる。サンチョの腕は温かく、パパスのそれとは少し違った力強さだった。 戦いに出る男と、帰る場所を守る男。その違いだろうかと、心地好く押し寄せる睡魔の中で思った。 目が覚めたらもとの俺の部屋でコントローラを握ったまま眠っていた――― なんて都合のいい展開を期待していたけれど、目を開けるとそこは昨夜眠りについたままの簡素な寝室だった。掌は相変わらず小さく、階下からは食卓の準備をしているのだろう食器のぶつかるような音が聞こえる。 ほんの少しだけ落胆した後、俺は起き上がって簡単に身支度を整えた。 階下に下りると既に食事を終えたパパスがのんびりとカップから飲み物を啜っているところだった。 『おはよう、サン。良く眠れたようだな』 笑顔のパパスにおはよう、と小さく挨拶すると、 『随分お疲れだったんですよ。ぼっちゃんはまだ小さいんですから。すぐに朝食をお出ししますからね。少しお待ちください』 使い終えた食器を片付け、新しい食器を棚から下ろしながらサンチョが笑う。 最後の一滴を飲み終えるとパパスは、傍らの荷物袋を手にすると一息吐く間もなく立ち上がった。 『サン、父さんはちょっと出かけてくるからな。いい子にしているんだぞ』 『おや旦那様、もうお出かけですか。折角ゆっくりなさられるかと思ったのに』 『うむ・・・、もう一仕事終えれば落ち着くからな。すまないがサンチョ、留守を頼む』 困ったように頷き、サンチョは扉の前までパパスを見送った。お気をつけて、とその背中に投げかけて、俺を振り返る。 『まったくお忙しいお父上ですな』 にこっと笑う笑顔につられて俺も微笑む。 さあ食事ですぞ、と出された料理は、ジャンクフード慣れしていた俺の舌に驚くほど美味かった。ふた皿分をぺろりと平らげ、ジュースのような甘い飲み物を飲み干し、一息つくと俺は「探検に行ってくる」とサンチョに言い残し家を出た。 今日は少し雲が多いようだった。太陽が時折雲間から顔を出し家々をなぞるように照らしていく。 俺はまず基本中の基本、村中の樽の探索から始めることにした。小さな村とはいえ建物の数はそこそこある。けれど屋外の樽や壷からは残念なことにめぼしい収穫はなかった。 気を取り直して入り口側から順に屋内の調査に取り掛かる。とりあえず一番近場の平屋の扉を開けると、キッチンから若い女があらあ、と笑いかけた。 『パパスさんの。ぼうや今日は一人なの?』 作り笑顔で応えると、女はにこにこと近寄ってきて俺の目の高さまで屈んだ。 『ぼうやも大きくなったわねえ。ぼうやがお父さんとこの村に来たときはまだこーんな赤ちゃんだったのよ?早いものねえ』 身振りを添えながらゆっくりと話し、俺の頭を撫でる。 正直、やりにくいな、と思った。ゲームならこっちからコマンドを入れない限り、相手は俺がいないと同じ振る舞いをするのに。こう話しかけられると簡単にタンスの中なんて漁りにくい。子供の無邪気さを武器にしたって、勝手に他人の家を荒らせば咎められるに決まっている。 面倒くさいな。 そう思ったところに後ろから老人が語りかけた。 『パパス殿はここに来る以前は一体何をしておったんじゃろうなあ。わしが見るに、あれは只者ではない筈じゃよ。ぼうやは小さすぎて、昔のことは覚えておらんじゃろうがなあ』 『おじいいちゃんてば、昨日パパスさんが帰ってからあればっかりなの』 くすくすと小声で笑い、 『きっとおじいちゃんはパパスさんに夢を見てるのね。おじいちゃんも、昔は旅をしていたらしいから』 耳元でささやくと、女はおじいちゃんお薬は?と老人に向かって立ち上がった。 王様だよ、と言ってしまおうかと思ったけれど、まあやめておいた。突っ込まれても困るし、パパスが隠しているんだから言うべきではないだろう。子供の幻想だと笑い飛ばしてくれる可能性もあったけれど、面倒ごとは起こさないことに今決めた。 老人と女のやり取りを尻目に、俺は奥の引き出しに目をやる。めぼしいものは、外から見た限りでは解らなかった。引き出しを開けてみる度胸もなく、俺は「探検の途中だから」と目一杯無邪気に言うと、家を後にした。 さて困ったのは、屋内の探索だった。念のため宿屋を覗いてみると、階下の酒場ではバーテンが忙しそうに仕込みをしていた。 「探検してるんだ」と言うとバーテンは愉快そうに笑って『ここにはぼうやの喜びそうなものはないなあ』と言った。言ったとおりで、隅の樽の隙間まで調べたが役に立ちそうなものは見つからなかった。 二階に上がりながら、まだビアンカ達が滞在していることにふと気付く。 手前の部屋は空き部屋だった。引き出しも空っぽだ。奥の部屋のドアをノックしようとした時中からおかみの『困ったわ』と言う声が聞こえた。思わず動きを止めて声に聞き入る。 『どうしようねえビアンカ。親方さん、まだ戻らないみたいよ』 『じゃあ戻るまでここに居ればいいじゃない。あたしまたサンと遊びたいな』 『そんな訳にも行かないでしょう。お父さんが待ってるんだよ。誰か探しに行ってくれないかねえ。パパスも留守だったしねえ』 とんとん、とそっと扉をノックすると『親方さんかしら!』とおかみの声と、軽い足音が聞こえた。 ガチャリと勢い良く開いた扉の向こう、ビアンカの顔が輝くのと同時に、その奥でおかみの顔が少しだけ残念そうに曇る。 「こんにちは」 努めて明るく呼びかけると、ビアンカが 『遊びに来てくれたのね!嬉しいわ!』 と本当に嬉しそうに俺の手を引いた。 『そうだわ、今度はあたしのご本を読んであげる』 部屋に入り傍らのベッドに腰掛けるとビアンカは飛び跳ねるようにくるくると室内を行き来、自分の荷物袋から一冊の絵本を探し当てた。 『この村って大人しか居ないんだから。あたしずっと退屈だったのよ。サンが居て良かったわ』 にこにこと喋りながら、俺の隣にぴったりと座りお互いの足に渡らせて大きな薄っぺらい絵本を開く。 『あたしの住んでるアルカパには男の子が居るけど、みんな子供っぽくって。じゃあここからよ。あたしが読んであげるからあんたは絵を見ていればいいわ』 妙にませた口調を使うビアンカにおかみはくすくすと笑いながらまた不安げに窓の外に目を落とす。 『すてきな、なかよしよにんぐみ。かしこいボロンゴ、やさしいプックル、かわいいチロル、ゆうかんなゲレゲレ。・・・聞いてるの?サンってば』 ビアンカの指摘に慌てて本に視線を落とす。昨日見た本よりも明らかに少ない単純な文字が並び、ページを大きく使って賑やかな絵が描かれていた。 『・・・もう。いい?ここよ?みんな、ちっともにていない。とくいなことも、すきなたべものも、ぜーんぶちがってる。』 ビアンカの声と文字をなんとなしに追っていく。この世界の文字はまだ読めないが、それでもゆっくりとしたビアンカの声にあわせて文字も理解できるような気がした。 おかみが溜息をつく。 「どうしたんですか?」 悪いとは思いながらもビアンカの声を押しやって、知らない振りで俺はおかみに声を掛けた。きょとんとした顔のビアンカと、困ったように笑うおかみ。おかみの顔から目線を外さずに居ると、やがておかみはもうひとつ溜息をついた。 『ごめんね、あんたにまで心配かけちゃ悪いね。なんでもないんだよ』 そう言うと俺とビアンカの座るベッドの前に屈み込み俺の頭を撫でた。 『・・・もうご本はいいみたいね』 面白くなさそうにビアンカが呟いた。 また今度、俺がもう少し文字を覚えたら。無理矢理の約束を取り付けて、俺はそそくさと部屋を辞した。 宿屋を出ると、日は随分と高くなっていた。雲から外れた太陽が俺の足元にも小さな影を作る。 パタパタと駆け出して、俺は小川を渡り村の奥に向かった。教会の裏を抜けて傾斜を上がると、洞窟のような入り口に申し訳程度の看板がかかっているのが見えた。文字はやはり読めない。 そっと扉を開くと、店先のカウンターには誰も居なかった。頭を突っ込み奥を覗き込むと、若い男が一人心配そうに忙しなく室内を歩き回っている。上の空の状態で、声を掛けてもすぐには俺に気付かなかった。 『やあ、ぼうや。悪いけど店はお休みなんだ』 小さな訪問者に慌てて笑顔を作った男の表情からまだ不安の色は消えなかった。まいったなあ、としきりに口元に手をやって、落ち着きなく体を揺らす。 「親方さんはまだ戻らないんですか?」 尋ねると意外そうな顔で『ぼうやも知ってるのかい?』と声を上げる。 『いつもならもう戻ってるはずなんだけど。何かあったのかなあ。俺が探しに行きたいんだけど、擦れ違ったら厄介だしね』 よく見れば奥のテーブルには薬草と幾つかの装備品が投げ出されていた。この男も葛藤してるんだな、と何となく思った。 「じゃあ僕が探しに行くよ」 俺が言うと男は困ったようにその整った顔を崩して 『ぼうや、ありがとう』 と言った。子供のたわ言だと思っている顔だった。 方向を変え、村はずれまで歩く。只でさえ森に囲まれた村道は、洞窟近くになるとさらに深く影を落としていた。 洞窟の入り口は目に見えてわかりやすかったが、くぐもったその先に足を踏み入れるのはやはり少しだけ躊躇われた。村までの道のりはパパスがついていたから不安はかなり小さかった。今回は頼れるのは自分ひとりだ。しかもこの奥は記憶が確かならおおきづちとかが出るはずだ。 痛恨を食らったらどうなるか。あまり想像したくない。 自覚している以上に緊張していたのか、肩を叩かれるまで声に気がつかなかった。はっと息を飲んで振り返ると、緑に映える鮮やかな赤い鎧を着た男が心配そうにこちらを覗き込んでいた。 『ぼうや、大丈夫か?どうしたんだ?』 額の汗を手のひらで拭って、俺はひとつ深呼吸をした。 「大丈夫。ちょっと探検に行くんだ」 我ながら固い口調だったが、鎧の男はふんと頷いて、 『この先の洞窟か。ぼうやには少し、危険じゃないかな』 諭すような声色で言う。 どうしても中が見たい、一人で行きたい、と子供らしく駄々をこねると、男は 地下には降りないこと 危なくなったら大声を出すこと(反響して入り口にも声が届くから) という二つの約束を俺にさせ、『迷子になるなよ』と笑って送り出してくれた。 入り口から数歩進むだけで外の明かりは洞窟内にはもう届かなくなった。どこかに光源があるのか、中はぼんやりと進むのに支障がない程度に照らされている。 右手から僅かな水音が聞こえるのは村の中央に流れる小川の水源だろう。モンスターはまだ姿を現さないが、岩壁の向こう、もしくは背後に今にも奴らの呼吸が聞こえてきそうで俺は唯一の武器、木の棒を握り締めながら慎重に進んだ。 手前に分かれ道が見える。陰から何か飛び出してくるんじゃないかと息を詰めたが、奥を見渡してもまだモンスターの気配すら見当たらなかった。左に向かう道に進む。 水音が背後に回る。その音に混じったキキッ、という小さな鳴き声を俺は聞き逃さなかった。反射的に振り向く。向こうは足元の岩陰に隠れたが鮮やかな青い色を視界の端に捉えた。 スライム。一匹だけか。 足音を殺しながら一歩踏み出そうとした時、今度は背後から衝撃を受けた。それに合わせるように手前のスライムが岩陰から飛び上がる。 もう一匹いた。 囮だったのか。 頭使いやがる。 なんだこいつら。 思考が頭を巡る間に近付いてくる最初のスライムのつるんとした質感。俺は咄嗟に右手の木の棒を振り下ろした。 ばちん、と衝撃音がして、スライムが地に転がる。立て直してくるかと思ったが、それはそのまま沈黙した。もう一匹がピキーッと甲高い声を上げる。それに向けてもう一度棒を振り下ろすと避ける間もなくスライムは地面に転がって動かなくなった。 ・・・強くなってる。 そう直感した。パパスの背に隠れて、殆ど攻撃を与える機会はなかったのに。ちゃんと強くなってる。 不意に緊張が解けるのがわかった。スライムの死骸から小銭を抜き取ることも忘れずに、俺はさらに奥へ進んだ。 分岐の奥は行き止まりだったが(勿論わかっていた)奥に打ち捨てられたような、小さな箱が転がっていた。手に取ると端のほうからぽろぽろと木の屑が落ちる。壊すようにして蓋を開けると中から薬草の包みが転がり落ちた。それを腰袋にしまいこみ、俺は来た道を戻った。 レベルは上がっていく。それがわかって、俺は少し安心した。適度に戦闘をこなしながら行けばこの洞窟は問題なく最深部まで辿り着けるだろう。武器が木の棒だけと言うのが不安だったが、まあなんとかなる。 何度かスライムや、土から顔を出した昆虫みたいなの(名前忘れた)を叩き潰して俺は突き当たりの分かれ道に差し掛かった。右からは水音。左側は道が湾曲していて奥は見えない。 俺は迷わず左の道を行き、最初の階段を下りた。 下り切ったところは、左右に伸びる道の真ん中だった。どっちだっけ、と僅かな時間考え込む。宝箱が幾つかあったはずだから歩き回っても問題ないだろう。そう考えて俺は、そこから左に向かう道のほうへ歩き出した。 すぐに右手に分かれる道が見える。曲がって進むとすぐに突き当たったが、装飾のはがれかけた荷箱の中から小銭袋を拾った。中身は確認せずそのまま自分のものにする。 少し戻りさらに進むと、僅かに水音が聞こえてくるのがわかった。視界が開ける。 大きくはない、けれど渡れそうもない洞窟内の湖だった。上階の水源から染み出してくるのか、壁伝いに幾つか筋が出来て透明な水が湖に流れ込んでいる。 どこからか同じように水が流れ出しているらしく湖は一定の深度を保ったまま静かにたゆたっていた。水面を覗き込むと恐ろしく深い。底は見えない。奥まったところには中瀬のような陸地が出来て誰が使うのか階段が設えてあった。 こっちじゃないな、と俺は思う。 スライムや、昆虫や、どらきち(早く仲間にしたい)とかを叩きながら道を戻る。反対側の道が開けてまた左右に分かれる道が出来ていた。ここは繋がってるはずだからととりあえず右へ曲がるとぐるりと迂回した向こうに木箱がひとつあるのが見えた。 期待を込めて駆け寄る。中身は――盾だ。皮をなめして貼り付けただけのような粗末な盾だったが俺にはありがたかった。これで随分と楽になるだろう。 意気揚々と進んでいくと、また分かれ道に出た。盾を手に入れた安心感から俺は何も考えずに左へ進む。行き止まり。 戻ろうと振り向いた時、今までとは違う低い鳴き声が洞窟に響いた。反響から一瞬。相手の居所がわからない。 慌てて見回した俺の目の前。岩陰から不意にそいつは姿を現した。丸々として、異様な毛を蓄えた外観。手にした大きなハンマー。出た。おおきづちだ。こいつの一撃がやばいのはわかっていた。慎重に少しずつ後ずさる。背後に、今後にしたばかりの、壁。 そいつがぐう、と低い鳴き声をあげると陰からもう二匹のおおきづちが姿を現した。追い詰められた。やばい。 盾に安心して回復を怠っていたことをはたと思い出す。左腕の痛みが不安と同じ速度で体を巡っていく。 薬草を取り出そうとした刹那、一匹がハンマーを振り上げた。つんのめる様に壁沿いに身をかわす。やつら、やっぱり動きは遅い。これなら避けられる。 もう一匹の攻撃を盾で受け止めると相手は芯を外したようで跳ね返って転がった。痛んでいた腕が更にじわりと熱を持つがまだ致命傷には遠い。右手の棒で一匹の動きを捉え、叩きつける。ぐう、と一声鳴いてそいつは後ずさったが、相手にも致命傷を与えることは出来なかった。敵の目に、怒りの色が滲む。 ちっと舌打ちした次の瞬間、背中に重い衝撃を受けて俺はよろめいた。体を捻ってどうにか尻をつく。攻撃に気を取られて、背後への注意が疎かになっていた。肩口がひどく痛む。痛恨だ。くそ。 薬草を取り出そうと腰袋に手を突っ込んだ時、最後の一匹がハンマーを振り上げるのが見えた。咄嗟に両手を目の前に掲げるが、間に合わなかった。 視界が暗転する。 『ぼうや。ぼうや、気がついた?』 涼やかな女の声に、俺は目を開けた。様々な色が眩しく俺の上に降りかかってきて、眉間に皺を寄せる。 『ああ、よかった。気がついたのね。神父様』 女が呼びかけると、隣で何か呟き続けていた男が声を止めて組んでいた手を解いた。 『洞窟の奥で倒れていたんですって。少しやんちゃが過ぎるんじゃないかしら』 身を起こすと、女が優しくそれを支えてくれた。教会の中だとすぐに解った。ああ俺死んだんだな、とまだぼんやりと霞む頭の中で思う。 なんかの映画で見たのと同じ、色ガラスを組み合わせた天井から光が差し込み白い床に不思議な模様を描いている。紺色の修道服姿のシスターと、刺繍が施された真っ白い衣服の男。これが神父様、か。 『彼が見つけて運んできてくださったのよ』 示す方向に目をやると、少し離れた椅子に赤い鎧の男が心配そうに腰掛けていた。 『戻るのが遅いんで、探しにいったんだよ。まさかあんな所まで降りているとはな』 約束を破ったな、と男は微笑んで見せる。 ぺこりと頭を下げると男は立ち上がって、真新しい小さな布袋を俺の膝の上に置いた。中から金属のこすれるような音がする。中を覗くと何枚かのコインが色ガラスを反射して虹色に光っていた。 『袋が破れていてな。出来る限り拾ったが・・・足りていなくても恨まんでくれ』 『あら、助けていただいて恨むなんて』 少しばつが悪そうな鎧の男に、シスターが笑う。鎧の男とシスターを見比べながら俺はありがとう、と口にした。シスターの頬がほころび、男が照れ臭そうに兜の上から頭をさする。 『お父様とサンチョ様には内緒にしておいてあげる』 というシスターにもう一度礼を言って俺は鎧の男と連れ立って教会を後にした。日はもう傾きかけ次第に橙色に染まっていく太陽が点在する家屋を照らしている。 『ぼうや、もう無茶をするんじゃないぞ』 兜の奥の瞳を少しだけ細めて男は言いながら、腰を落とした。真っ直ぐに真剣な眼差しが、俺の両目を捉える。 『正直、ぼうやを見くびっていた。ぼうやは勇敢な子だ。でもな、勇敢なのと、無茶をするのは少し違う。わかるな?』 俺がはい、と頷くと、男は満足げに俺の頭を撫で『さて仕事に戻るか』と踵を返した。俺はもう一度頭を下げると、夕暮れ色に染まっていく空気の中帰るべき我が家へと歩き出した。 リセットしてえええ と思ったが無理な話だった。大体にして、この世界でセーブなんてどうしたら良いのか解らない。教会で『セーブひとつ』『リロードひとつ』と言ったら聞き入れてもらえるんだろうか。 念のため明日試してみようかな。首をかしげながら、俺はその日の床についた。 家での動きは昨日と殆ど変わらなかった。サンチョの腕に抱かれると心地好い睡魔が押し寄せ目を覚ますとパパスが『仕事が片付かん』と言いながら出て行く。見送るサンチョとともに食事をし、俺は「今日も探検」と言って家を出た。 朝の日差しは眩しかった。まだ上りかけている太陽が色鮮やかに緑の木々を染め上げている。 今日の俺は昨日とは違う。呟きながら俺は迷わず武器屋の方へ向かった。袋の中の小銭と相談しながら、品揃えを眺める。武器屋の店主は簡単にそれぞれの武器の使い方を教えてくれた。中から、動物の骨を削っただけと言う長めのナイフのようなものを選ぶ。 なけなしの小銭をはたくと奥からおかみさんが顔を出してこちらに笑顔を向けた。 『随分小さいお客様ねえ』 ころころと笑うとちょっと待って、と部屋の中に取って返し、 『ずっとタンスにしまってあったんだけど、うちじゃ使わないから。おまけね』 そう言って俺に薬草をひとつくれた。礼を言って武器屋を出る。新しい武器を何度か素振りすると、なんとなく自分の手に馴染んだような気がした。 洞窟に入る前に教会に寄る。シスターに改めて昨日の礼を言い神父の下へ向かった。 「お祈りをしたいんですけど」 俺が言うと神父は穏やかに目を細めて祈りの言葉を口にする。 セーブ音を期待した。だが、何も起こらなかった。 洞窟の入り口まで行くと赤い鎧の男が『また来たのか』と笑った。買ったばかりの武器を見せ無茶をしないこと、とだけ約束をして、俺は二度目の冒険に出た。 昨日よりも明らかに体が軽かった。受ける衝撃も随分軽く感じる。寄り道はせず、真っ直ぐに地下へ降り更に階段を下りようとしたところで、また三匹のおおきづちに出くわした。 体力は問題ない。先制して新たな武器を振り下ろす。その衝撃に、芯を捉えた事が自分でも解った。おおきく体を仰け反らせて、一匹目が動かなくなる。残りの二匹に動揺が走るのが解った。足を止めず、攻撃をかわす。 攻撃。回避。防御。 一発痛恨を食らったが、それだけだった。二匹目、三匹目が倒れ、俺はほっと息をついた。 その時。 不意に頭の中に何語ともつかない声が浮いた。辺りを見回す。誰も居ない。話しかけられたような感じもない。俺の頭に浮いたそれは、すぐに形を失い今はもう静寂が辺りを包んでいる。 あ、と思って俺はもう一度意識を集中してみた。回復、回復、ホイミ。 また、何語ともつかない声が脳を支配し、俺は自分の意思ではなく喉からそれを発していた。丁度今、おおきづちにやられたばかりの傷みが空気に溶けるように消えていく。 レベルが上がった。それは初めての実感だった。 三匹の亡骸を背に、俺は階段を下った。 右にそれる道を無視して、真っ直ぐ奥へ進む。開けた空間の中ほど、大きく散らばった幾つかの岩の傍ら地面に寝そべるいかつい老人の姿が見えた。親方だ。物凄く長い道のりだった気がした。傍によると、親方はぐふう、と息を吐いて寝返りを打つ。 つか本当に寝てんのかよ。緊張感ねーな。 呆れ返りながら俺は、親方の肩を揺さぶった。うん?と口の中をもごもごさせながら親方が体を起こす。 『おや、ぼうや。こんなところで何をしているんだい』 本格的に緊張感のないのんびりした口調で、親方が言う。俺はがっくりと肩を落としながら「助けに来ました」と言った。おやまあと目を細めて、親方が続ける。 『そうかい、ありがとうよ。じゃあちょっとこの、岩を押してくれんか。動きそうで動かんのだよ』 そういって目をやる岩の下に親方の片足が痛々しく押し潰されていた。濃い色のズボンを破って、肌から赤黒く乾きかけた血が滲んでいる。 『隙間に引っかかっているようでな。傷は大したことないんだよ』 不安そうな目の色を察してか、親方がゆっくりと言う。 『ただ押しても引いても抜けんもんでな。いや参った』 わかりましたと頷いて俺は岩を押しやるのを手伝った。しかし岩は大きく重く、子供一人の力が加わったところで動きそうもない。なんでやねん。また約束が違う。 『やれやれ。やっぱりだめか。ぼうや、誰か大人を呼んできてくれると助かるんだがな』 子供のプライドを気遣ってか出来る限り優しい口調で親方が言う。俺は大人のプライドを持っていたので、逆に悔しかった。辺りを見回す。 ふと思いつき、散らばった中から適当な大きさの石を拾って俺は親方の足の傍に置いた。売り忘れて持っていたかつての武器を手にする。岩の隙間に片端を差し込み、俺は石を支えに反対端に思い切り体重をかけた。僅かでも浮けば。僅かでも。 考えを察したのか、親方が空いた隙間に手を押し込み力を加え、更に自由な方の足を岩の隙間に捻じ込んだ。木の棒が嫌な音を立ててしなる。頼む、と俺はさっき祈りをささげた神に祈った。 不意にずるりと、親方の足が抜けた。かかっていた重力が瞬間的に緩み、からりと乾いた音を立てて棒が転がる。同時に、詰まらせていた二人分の呼吸と笑い声が空間にこだました。 『いや、ぼうや。助かったよ。賢いねえ』 肩で息をしながら親方が微笑む。照れ笑いを隠して、俺は棒を拾い上げ腰布に差し込んだ。 親方の傷は本当に軽そうだった。凝り固まった体を解しながら足首を回し、『うん、大丈夫そうだな』と言うと意外なほど身軽に立ち上がる。 『ぼうやありがとうな。みんな心配しているだろう。早く村に戻らねばならんな。行こうかい』 手を引いて歩き出そうとする親方の申し出を断って俺は洞窟に留まると伝えた。「もう少し探検してすぐ帰るから」と言うと、親方は 『こんな洞窟でも、ぼうやには大冒険だろうな』 と笑い、こちらを気にしながら一人階段を上がっていった。 簡単に洞窟内の探索を進める。最深部でも、出てくるモンスターの種類は殆ど変わらず、俺はスライムや昆虫や角の生えたウサギを叩きながら分かれ道の先を覗いていった。奥に朽ちた空き箱がありその縁に布切れが引っかかっている。手に取ると着衣のようだった。今の俺の服よりは、少しだけ布が厚く縫製もしっかりしている。 その場で着替えるのはなんとなく気が引けて、俺は軽く埃を落とすと服の上からそれを羽織りひとつだけボタンを留めた。 反対の奥にはスライムがいた。咄嗟に武器を構えると、『叩かないで!僕は悪いスライムじゃないよお!』と慌てたようにその大きな口から人間語を発した。話を聞いてやると、三角だか四角だかよく解らないことをまくし立てるように喋っている。(こんなところはゲーム通りかよ) それ以上の収穫はなく、俺は久し振りの人間語を話したがるモンスターに達者で暮らせよ、とだけ言い残し帰路についた。 洞窟を出ると、赤い鎧の男が笑顔で手を挙げた。 『さっき薬屋の親方が通ったよ。ぼうや、親方を探しに行ってたんだってなあ』 頷くと、感心したように男は顎に手を当て、 『何も言わずにこんな洞窟の奥にな。恐れ入ったよ。でも次はおじさんにも相談してくれよ。なんにせよ危険なんだから』 にこにこと勝手に頷きながら、男が俺の頭に手を置く。 言ってもどうせついてこないだろ。っつか俺を探す前に親方を探せよお前。 思ったが恩があるので黙っておく。 簡単に挨拶を済ませ俺は親方の家へと向かった。そろりと扉を開け顔を出すと、店員の若い男が俺に気付いて明るく笑った。表情の奥にも、もう不安の色は見えなかった。 『ぼうやは昨日の。今日も来てくれたのかい?親方、さっきやっと戻ったんだよ』 言いながら丁寧な物腰で俺を奥に通す。 『親方、この子昨日も心配して来てくれたんですよ。知り合いなんですか?』 『うん?おお、おお、ぼうやは洞窟で会った』 薬の調合なのか、秤や見たことのない器具とにらめっこしていた顔をこちらをに向け、忙しなく動かしていた手を止めて、親方が嬉しそうに笑みを零した。え?と声を上げる若者に、親方は 『洞窟まで探しに来てくれたんだよ。そうだ、お礼をしようと思っていたんだよ。丁度良かった。ちょっと待ってくれんかな』 言いながら立ち上がり奥のタンスに向かう。僅かに引きずった片足に、真新しい白い包帯が見え隠れしていた。あの時は無理をしていたんだと、その時になって気付く。 『ぼうや本当に親方を探しに行ってくれたのかい?』 驚きを隠さずに若者が言った。頷くと男は、声にならないと言う表情で、俺の顔を見つめる。 「探しに行くっていったろ?」 俺が言うと、若者はあはあ、と笑って 『参ったな。ぼうや強いんだなあ。俺、実はちょっとあの洞窟が怖くってさ』 頭を掻きながら極まり悪そうに言った。正直な男なんだな、と思い俺もあわせて笑った。 ほれ、と親方の手から差し出されたのは網目の粗く薄いケープだった。派手な色の糸を編み合わせてあって、ちょっと俺には着れないなあと失礼なことを思った。 『わしの手編みだよ。出来は良くないがな、ここが入っとるんでな』と胸に親指を当てながらにやり笑う親方にお礼を言い、丁寧にお礼を言われ、俺は親方の家を出た。 宿屋にも顔を出そうか迷ったが、疲れていたし面倒だったから俺はそのまま家に足を向けた。パパスは戻っていなかった。 まだ陽は高かったが、早めの夕食をとるとすぐにサンチョが俺を抱きかかえたので睡魔に身を委ねて俺は目を閉じた。